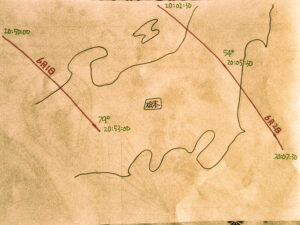正直勝てる気がしない、と思いつつプレビュウで懸念したことが、ほとんどミゴトに的中してしまって、言葉もない。
GK圍の先発はともかく、上門と山本によるゴール、コーナーキックからの失点(by 喜山)。
その結果、全方位ホーム環境下での完敗、ときたもんだ。
予言した者として謝罪しなくちゃならないのか?、と道義的な責任を感じてしまう。
〈隙を見せずに隙を突け〉とは、マッチデイプログラムの見出し。
かえってファジアーノのほうが、それをやって魅せたんだから、記事のライター氏も、皮肉な結末に、さぞや、激怒の無念に違いない。
先制してからの岡山の試合運びは、ほほ完璧。
プレイヤーの距離を遠くしておいてボールを動かすことで、山雅にボール奪取のポイントを絞らせず疲弊させ、攻撃への反転を空回りさせた。
というよりも、こちらがまるでミス繰りだしのオンパレード、かつ、セカンドボールが拾えなかったら、ああなるのは当然だ。
まるで、敗戦する時は、3点を差し上げる、って決まりでもあるんかいな、と思わせるほどに、チームの意思統一が低下し、散漫となり、弛緩する。
圍が必死でセーヴィングしてポストを叩いた上門のシュート。
あれが決まっていれば、あわや、4点の献上だった。
― かつては、ゲームにやり切った感が在ったんだけど、今はなし。
どんなサッカーをやりたいのかが不明。ヘディングもただ身体に当てるだけのことだし……、と山雅ウオッチャーとしては先輩格の娘から、メールが入る。
まことに、ごもっともな指摘だ。
山雅のシュートで、枠内に飛んだのは、外山 凌のゴール、1本だけだったか?
事故みたいなゴールを期待しなければならんほど、ボランチから前線と2列目へ対し決定的なボールが入ってこない。
2列目は2列目で、中盤のボールさばきにあくせくとは、なんとも。
これ、前 貴之を右サイドバックに配置せざるを得なかったからだけなのか?
といっても、外山と下川 陽太が創る左サイド攻撃にしても、外山の外側を上がる下川にボールは、チットモ出て来なかった。
練習で出来ないことは本番でも再現できまい、と思うんだが、何に手をつけているんだろう?
万策尽きたのでバンザイのグリコ、でもないでしょうから、そこをせいぜい悩んで、克服してもらうしかありませんな。
ゲームのところどころで、原石がキラリと光るぐらいでは、満足もできなくなっているのですよ、アルウィンは、もはや。
〈侮蔑の拍手は 差し上げない〉
現行の応援制限は、ファンサポーターには、とってもアンフェア。
不平や不満を、口に出してチームに訴えることができないからだ。
それとも、ゲームの途中で皆が一斉に帰り始めれば、わかってもらえるのか。
そこで。
今回はじめて、ゲーム後に、ゲートフラッグを逆さまに掲げ、挨拶にまわるチームに不満!!を表明させてもらった。
別に、佐藤 和弘や前 貴之に個人的な恨みをモノ申しているわけじゃあないが、こんなゲームだったら、単なる拍手を貰うほうがむしろ、彼らにとって恥ずかしかろう。

最後。
ゲーム後アルウィンの拍手が、もちろん!!、岡山プレイヤー側に倍して大きかったことを書いておきます。
では。