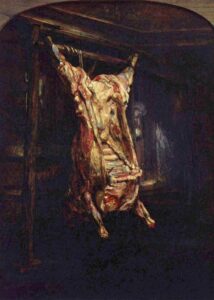註) 既に散った、だいこんの花、白☞紫のグラデーションが美しい。
……山雅について。
八戸戦レビュウから導けることは、
現状レベルのゲーム運びと、ボール運びを続けている限り、
(以前からの僕の読みでもあるけれど)
勝ち負けが交互に現れて、最終盤、勝ち数が、負けのそれよりか数個多くなる。
で、3部リーグは、序列格差があまりなく実力フラットなので、勝ち点基準は下がる傾向にあって、
結果、相対、順位がプレイオフ圏内に……というのが、希望的な観測。
それ以上に戦績が上向けば、もちろん、素晴らしい。
ここで。注文をつけるなら。
実直な正攻法に磨きをかけることを、より深めるべきだけれど、
もっと、トリッキーな、別の言い方だと、豪胆な巧妙さ、を追求するべき。
たとえば。
(コーナーキック数はリーグトップなんだから) デザインした セットプレイを立て続けに見舞う。
あるいは。
長野戦のゲーム冒頭でみせたような、基底から組み立てる、と見せかけて、センターバックが猛烈ダッシュ、同時に、大内がロングボールを蹴り上げる、そんな工夫。
それには、肉体的に走れるは当たり前で、フルタイム、頭が相手の予想より素早く回転しつづける〈体力〉が要るだろう、と昨日、書いた。
他にも課題はあるだろうが、山雅の奮戦には、まだまだ可能性があろう。
実は。
それよりも、ずっと苛酷な戦いを強いられているのが、この萬年。
数週間前から、家庭菜園の中を、モグラめが一匹、縦横無尽に走り回り、ミミズバレに土を盛り上げて、トンネルを掘りまくっている。
対し、トラップを仕掛けるなどして、とにかく、庭にだけは入らないようにと苦戦中。
つまりは、いまだに捕獲、あるいは、奴めの逃走には至っていない。
で、昨日やってきた息子が、
モグラとの交信によって追い払うのがいい、という。
訊けば、彼、小学生時代にやった実績があるらしい。
モグラは、縄張り意識が強く、単独で生活している。
その習性を利用して、
地面を叩くことで〈Go Away from Here!!〉のメッセージを送ると、
地中のトンネル上部を鼻先で叩いて、返信してくるのだそうだ。
それを執拗に繰り返して、ついには、根負けしてこの地から去ってもらう、というストーリー。
しかし、まぁ、コップを地面にあてて、さかんに地表を叩き続けるジジイの姿は、これまた、異様であるまいか?
……とは思えども、梅雨の今、なりふり構わず、あらゆる手段を使ってでも、
この希望なき戦いは続くのです。
では。