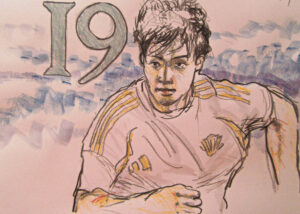パルセイロの、直近2ゲームは、
FC大阪、グンマとやって、つづけて、スコアレスドローだった。
山雅が一敗地にまみれたふたつとの対戦を、無失点で切り抜けているのだから、
そこだけにフォーカスすれば、そのサッカーの優秀性を認めるべきだろう。
ただ。
このスコアレス、ってやつが曲者であって、
長野は、我らとの対戦後、8ゲームを消化して、
得点 3、失点 5 (無得点と、無失点の試合が、ともに5つ)。
つまり、被弾をそこそこ抑止してはいるが、得点不足に悩む、ってのが、現状。
極論だと、パルセイロの喫緊の課題は、とにかくゴールを獲ること、それ以外にはないはず。
長野のゲームをほとんど捕捉していない僕だけれど、そのやりたいところは、おそらく、
〈ボールを保持しゴールに直結する速い攻撃〉〈相手陣内で主体的にボールを奪いに行く守備〉、と診る。
近年では、ボール保持を、もっとも高めているといったデータもあって、
その攻守を、3バックでやる。
……なんだよ、それだと、山雅と、大して変わり映えしない、とも言えて、
しかも、相当に攻撃的な意気込みでやってくるだろうことは、目に見えている。
……そうであれば。
乱暴な話、勝敗は、ほとんど、彼我の、個々の技量差で決まってくる。
(その事情は、まさに、サッカーの原理かも知れませんがね)
目の前の相手を、出し抜き、はがし、(正当なチャージで)フッとばしてでも前進せよ。
山雅の戦士よ。
自分たちが開発し、磨き、たくわえてきた自流が表現されて、
そこに、責任有するプレイが継続すること、を願います。
なお。上記〈〉で示してサッカースタイルは、
2週間前、石丸 清隆氏を新監督に迎えた際の公式リリースで、FC岐阜の現場筆頭責任者がステートメントしたものの抜粋。
次節のホーム岐阜戦には、それを標榜するチームがご来松、という次第です。
では。