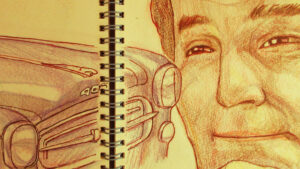今朝は、春の雪。
2月28日の夜に。
友人からショートメールが入っていた。
― ジーン ハックマン亡くなりましたね。エネミーラインや、ポパイ渋かったです。
〈フレンチコネクション〉(1971年 米映画)で演じた、
ニューヨーク市警察の麻薬課のドイル刑事。そのあだ名が、ポパイでした。
好漢、悪漢、どちらも上手くこなせる俳優だった。
さらに他の作品を、いくらでもとめどなく、引き合いに出したくなるけれど、ここは我慢して、
フレンチコネクションでは、相棒のロッソ刑事役を演った、ロイ シャイダー(1932~2008)が、良かった。
あだ名が、クラウディ(cloudy)なんで、その性格が〈暗い〉。
クラウディが、颯爽としたアメリカントラディショナルの着こなしで、
ポパイの強引な捜査に嫌々ながら(憂鬱に)つき合う、ってところがなんとも味があった。
(コンビを組む刑事物のはしりでもあったか)
ロイ シャイダーは、
後年の、ジョーズ(1975年)の警察署長、マラソンマン(1976年)での実業家(ダスティンホフマンの兄として) のほうが、世に有名かも知れない。
……と、ここまで書いて。
訃報に接しては、故人を偲ぶ自分に、少々ウンザリときてしまう。
存命であろうとなかろうと、
今の今だって、誰かに思いを馳せたり、できれば、その人のため時間を使わなければいけないのに……と。
ま、せっかくなんで。
おふたりのご冥福を祈りつつ、
フレンチコネクションから、車のロッカーパネル内に、密輸された麻薬を見つけ出すシェーケンスをご紹介します。
では。