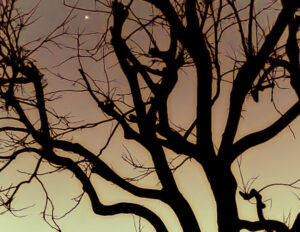ジム ホールは、ビル エヴァンス『Undercurrent』(1962年発表のアルバム)で、そのギター演奏に出逢っていたから、馴染みはあった。
だから、図書館で、彼の名を冠した『アランフェス協奏曲』(1975年)を見つけた時も、まぁ、ひとつ聴いてみるかぐらいの軽い気持ちで借りて来た。
ところが、早速、車中で流してみて、これはただごとならぬ好演奏ではないか、と驚いてしまった。
ジムのエレクトリックギターはともかく、一緒に演ってるメンツに呆れてしまう。
トランペット☞チェット ベイカー、アルトサックス☞ポールデズモンド、ピアノ☞ローラ ハナ、ベース☞ロン カーター、ドラムス☞スティーブ ガット……か。
これだけのメンバーが、呼吸乱れず、かつ、各パートを自在に演奏しているんだから、これだけの絶品になるわけだ。
後で調べると、発表当時から大ヒットしたらしいが、なんでも後から追いついて聴いている僕のことゆえ、さも、自分が発見した大事件のように書いてしまう。
というわけで、今日は、このアルバムを流して岐阜へ向かうんです。
で、冒頭の、〈You’d Be So Nice To Come Home To〉(戻ってくれて嬉しい)を。
ジム ホールのギターには、切ない郷愁へと誘う魅力がある。
では。