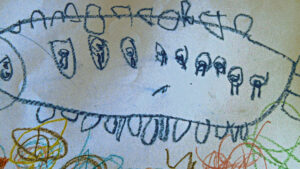セルジ―ニョの素晴らしいゴールで先制するも、立て続けのコーナーキックに堪え切れずに失点。
1 – 1 のドロー。
ゲーム後、スタジアムを一周するプレイヤーたちの表情には、ここで勝ち点3を逃がしたことの重さが、歴然でした。
終焉は一瞬では訪れず、一週間ごとにじわじわやってくる、って感じでしょうか。
そういうのも、なかなかしんどいですな。
ラスト5ゲーム、勝ち負けの星勘定は、萬年の予想どおりなんで驚きもしないが、こうやって現実化すると、スタジアムには、どうやったって、敗残と諦観の空気が押し寄せます。
しかしながら、ゲーム内容や、チームとしての出来は、いままでにないほどに高まっていた、と診ます。
❶初期システム 3 – 3 – 2 – 2 という最適解への習熟。
❷ほぼ最善と思われるメンツを、その布陣に落とし込めている。
(故障者の復帰を含め)
❸無責任なプレイが姿をほぼ消して、ボールが、湧き出て来るプレイヤーへと前向きに渡る。
❹球際の競り合いでは、執着心と鋭さが倍加した。
❺ファーストディフェンスの、行く行かないのコントロールに意思統一がなされメリハリがあって、相手の出鼻と態勢を崩せていた(チノ氏評)。
ボトムハーフに低迷するチーム同士の、突き詰められていないがゆえの甘さ、ミスが散見されて、順位はウソをつかないわ、といった緩慢なゲーム運びが感じられはした。
けれど、山雅としては、今季最上級の締まったゲームを遂行できた、と評価したいところ。
……、実は、北ゴール裏立見席の僕のすぐ後ろには、青年ふたりが観戦していたのですが、彼等が交わす言葉が、プレイと選手の技量に関する肯定的な内容であったこと、そういったことでも、大いに救われた。
こういう評言がアルウィンに満ちることを、切に願いますね。
誰と一緒に観るか?、でサッカーの価値も決まる、これはホント。
さてと。
いままでの40ゲームを、10試合ごとに区切って、山雅の、勝ち点奪取をみてみると……、
1~10 10
11~20 9
21~30 8
31~40 6
これには多分に、対戦相手次第という要素もある。
が、我らが戦いの出来に関しては、それなりにレヴェルを上げて来ているにかかわらず、勝ち点についちゃあ、尻すぼみ。
その根本的な事情として、すべてのチームが山雅以上に、ゲーム遂行の成熟度を高めていることが在る。
これに尽きますよ、おそらくは。
リーグ戦当初から引き摺ってきた、チームの作り込み不足が、他との比較でも、いかんせん挽回しきれていない。
良くはなっているけれど、滑走路が既に尽きかけている山雅号。
It’s Too Late……か、と心の中、呟やきながら、チノ氏と別れて駐車場に向かったのでありました。

旗振りとタオルぶん廻しが戻ってきたからには、土壇場は見届けないと。
相模原には参戦しますよ。
では。