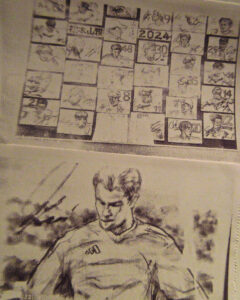仮に。
僕らが、感覚器官をとおして、実際に起こったのを見聞きしたことを〈事実〉と呼ぶとしよう。
対し。
過去に生起した事実に接した経験知にもとづいて、人が、
起こってもらいたい、起こるべきである、と願う、そのことを〈真実〉と呼ぶ。
実際には無かったが、現実ではほぼあり得ないが、
世の中、こういうことがらが起こっても良いではないか、と僕らが思うことです。
……ところで、
僕の家から、スープが冷めないほど近くに、
今年の一月に、ご長男を亡くした女性( A子さん)が住んでいる。
ある日、彼女から、
今度、息子の遺影を鴨居に飾りたいのだが、なにせ高い場所だから(こちらは女手のゆえ)、手を貸してもらえまいか、との電話があった。
あぁ、お安い御用です、都合の良い日を教えてもらえれば、すぐにでも伺いますよ、とお答えした。
で、つい、先日のこと。
A子さんとは(電話で)よく話すらしい、B子さんと、家人が電話で話した。
その際、B子が、
この前、A子から、
お宅のダンナに、息子の写真を飾るのを手伝ってもらいたいと頼んだら、
あぁ、ちょうど良い機会だから、その時に、ご長男を偲ぶ集まりでもやったらどうか?、と勧められた、と聞いたわよ、とのこと。
― まさかぁ。うちの亭主が、そんなことを提案するわけ決してないわ!、と家人は即座に否定した。
帰宅した僕は、その話を聞いて、いや、そんなことは言ってないなぁ。
こじんまりと内輪ではあっても、キチンと葬儀で弔っているのだから、
そういう、いわば、無意味な虚礼などは、僕にとってはまったく論外のこと。
……さて。
この、まるで僕を騙ったような顛末は、あまりに唐突で、印象深かったので、考え込まされたのだが、
単に、これを、A子の虚言(ウソ)で片づけるのは、間違っていて、
(誰が提案しようとも)亡き息子を偲ぶ会は、彼女にとって、ひとつの〈真実〉ではあるまいか。
つまり、起こってもらいたいこと、なのだ。
そして、なぜに、そういう集いが A子にとっては必要か?
おそらくは……、
そういう集いの中、周囲の者は、息子を失った自分に弔意を表すだろう。
その弔意こそ、彼女にとっては、自分の現在(喪失と悲しみ) に払われるべき同情と敬意であって、自分とは、それを受けるにふさわしい存在なのだ。
つまりは。
自分の存在価値を、僕の提案という形の架空な話を作り上げることで、他の人に認めてもらいたかった。
……どうも、人間は、かなり手の込んだことをやってでも、自分を価値化したいらしい。
もちろん、この〈真実話〉は、とっさにA子の口から出たはずで、彼女自身に、創作のカラクリなどは、まったく意識されていない。
今後、A子と話す時はかなり言葉に注意しなくちゃあな、とは思ったが、
世の、優れた文芸作品は、作者が、こういった〈真実〉を巧く駆使しているのだし、
事実と違うことを、それがすべてウソで押しとおすだからダメと断ずるほどに、僕は他人に冷淡にもなれないし。
こうやって、人間本性のホンネと深層に触れるのは、経験する意義もあることかも知れないぞ。
これからも、どこかで生みだされる彼女の〈嘘〉= 真実を、だから、ただ責める気にはなれない。
ただ、哀しいかな。
虚言を使ってまで愛と関心を求める者は、周りからは、ますます疎んぜられる。
……もちろん、
事実 = 真実の一本槍で生きたい者にとっては、以上、わずらわしいお話です。
では。