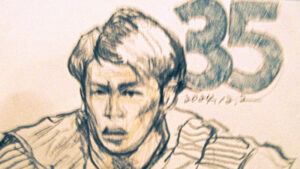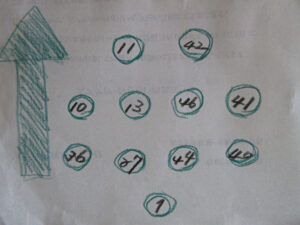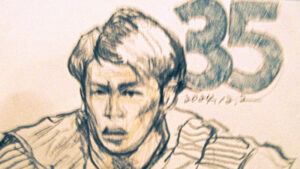
転がる石には苔むさず。
もともとは、
転々とばかりしていたら(責任から逃げ続けると)、成功は得られない、をいう諺。
だが、我が国のプロサッカーチームは、まるで、ローリングストーンのよう。
(諸外国も、事情は同じなのかな?)
経営マネジメントの一貫性という局面は別として、
フィールドマネジメントにあっては、
おおかたのチームが、毎年、 3分の1以上の顔ぶれを差し替え、
指導者は短命で、4年以上その職にあるのが、レアなケース。
で、上手くいかないと、年度途中の交代などはザラ。
人的資源を使いまわしながら、まるで、その年限りの決算と精算の繰り返し。
変わらないのは、取り巻くファン&サポーターばかり……なり。
……これが常態とは言え、こんなんでいいのかい?、とはしばしば思う。
さて、この前。
今季山雅のホームグロウン選手は 8名、と書いたんですが、実は、僕の勘定間違いで、ホントは、9名。(まことに失礼しました)
この数字を、リーグ全体の中においても (4/22 Jリーグ発表の数字による) ……
15人 ☞ FC東京
13人 ☞ 鹿島、広島
12人 ☞ 柏
11人 ☞ 大宮
9人 ☞ 東京V、横浜FM、松本
8人 ☞ 湘南、京都、G大阪、沼津 ……と堂々の数字なんです。(沼津も)
(☞ ホームグロウンとは、ユース年代に3年以上、または、高卒入団後 3年以上、そのチームに登録されること、をいう)
つまり、今の山雅の所帯は。
チームの 3分の1が、ティーンエイジャーから帰属した〈生え抜き〉と、高卒入団して3年経過、それに、育成型レンタル移籍加入の若手らが占めていて、
その上に、25歳前後の団塊が、チームの主体を成しつつ、
そこに、30前後のヴェテランと呼ばれるタレントをちりばめる。
事実、ゲームにはこのところ、ホームグロウン 6人が登録される傾向。
その限りでは、まことに有望な未来だろう。
この際、
転がる石は 滅びない、と読み替えてしまえ。
しかし。
この編成の根底には、
トップチーム人件費の圧縮による、売上に見合った経費コントロールといった、まことにシビアな経営マネジメントの要求も存するはず。
(育成型レンタルでは、レンタル元クラブに、出場機会を与えることを要件に給料負担を求められるだろうし)
かように、
みずから大きな変化へと舵を切ったマネジメント(経営と現場の)。
さて、それと共闘し支援すべきな、
取り巻きのファン&サポーターの理解度はいかがであろう?
ところで。
本日限りで、活動停止が解ける神田 渉馬よ、愚行など誰にでもあるさ、
前を向いてやり直せ、期待してるよ。
では。