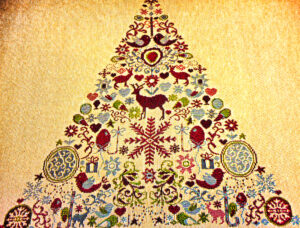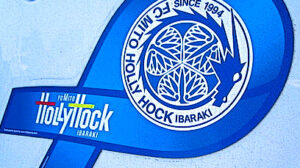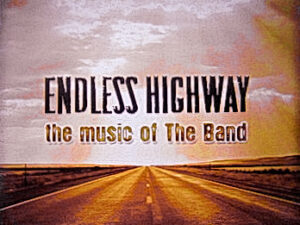〈水戸戦の宿題を書き上げる〉
第5節、対水戸戦。
山雅のボール保持率は、48%だった。
これ、山雅にしてはかなりの高値であって、ゲームの7割強を支配していたことの証拠でもある。
としたら、今節の相手が、ほとんど初物に等しい秋田であっても、勝利で終えるはずだった前節を、アルウィンの舞台でそのまま再現しなくてはなるまい。
〈柴田山雅 を再確認する〉
前回で描写したブラウブリッツのサッカーは、山雅にとってはいつか通った道にかなり近いけれど、今から、そこに帰ることはできない。
むしろ、苦杯を嘗めさせられたサンガのほうに感情移入してしまうわけだ。
ここで、昨季後半から今季にかけての、山雅の針路をくどい程に再確認……。
❶若手登用と成長をテコに、約束事を明確にしつつ、守備面の安定を図った。
❷前、佐藤らを補強、中盤における強度を上げると同時に、その攻撃性をより前線に近いポイントで発揮できるシステムを採用。
❸阪野をのぞいて、昨季戦力をごっそりと失った前線。
そこへ、チームとして新加入タレントを大量獲得。
実戦をとおして、個々の強みと、その組み合わせの最適解を模索中。
左サイド方面では、外山、河合が先頭を切るが、いまだ片鱗をも見せない人材は多い。
❹チャンスを活かしたDF野々村が売り出し中。橋内が復帰し、篠原が存在感をアピール。……、そんな感じか。
〈スタイルの組み合わせを 間違えない〉
どんなチームであっても、〈速攻〉はしたいし、しなくてはならない。
これはサッカーでは自明の理。
相手が帰陣して守備を整える前、広大なスペースがあるうちに攻め込めれば、ゴールのチャンスが大きいに決まっているからだ。
攻撃において、戦術として速攻を選ぶとすれば、相手をできるだけ我が側に引き付けておいて、ボールを奪って即反転攻撃、という策になる。
意識的に、敵を前がかりの態勢にさせる。
この時、相手の攻撃に堪える時間を無失点に切り抜けるためには、身体をはった〈堅守〉が絶対的に必要だ。
ガードを固めておいて、繰り出されるパンチ(攻撃)を敢えて受けるのだから。
つまり、〈堅守速攻〉とセットで呼べるのは、上のようなスタイルを基軸とする場合に限る。
二度のトップリーグ陥落の経験などを通過して、山雅は今、堅守速攻のサッカーを捨てた地点まで来ている。
その得点力の弱さゆえに、〈堅守〉はこれからも絶対命題だろうが、速攻でない攻撃(=ボールを保持して相手守備網を崩す)を研ぐこと。
これがベーシックな課題であるし、ここをクリアすることが、将来への布石になる。
編成されたチーム、タレントの面々をみると、この針路は明らか。
この視点からすると、(結果はともかく)、攻守に強度の高いゲームが続く今季であることは間違いなく、秋田戦にもそれを求めたい。
個々のプレイヤーへの思いは、挙げたらキリもないが、ともにキャプテンマークを巻く佐藤 和弘と中村 亮太。
中京大サッカー部同期の対決に注目しよう。
では。