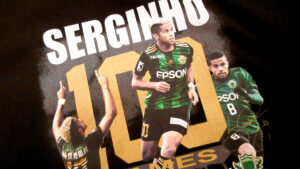スペインU24について、いまだに、考えています。
あのチームの容貌は、24歳以下の俊英を集めてつくった、ではなく、A代表のなかから24歳以下のプレイヤーをチョイスした、そういったもの。
だから強くて当たり前とも、日本代表に比して格が違った、とか言いたいわけでもない。
このチームが目指したものは、相手との比較の中にはなく、自分たちの技量をベースに、自尊するスタイル、やり方をひたすら追求することにあった、それを言いたいのです。
年齢構成とはまったく無縁の、彼らが自認するスペインサッカー、がそこにはあった。
たとえばそれは、ボールを、彼我でイーヴンにするような状況を徹底的に排除するサッカーだ。
繰り出すボールの長短におかまいなく、常にボールを我が支配下に置きながら攻撃を組みたてる。
だから、サイドに展開して深くえぐっても、簡単にはクロスを投じて来ない。
単純なクロス投入は、敵味方が半々に競り合うシーンを作るだけで、ゴールへの確実性を低下させるから。
こういうのを、人によっては、ボール支配を追求したサッカー、と言うんだろうけれど、そういったこだわりに忠実な分だけ、わかりやすくて、ある意味、予測可能だった。
日本がつけ込むとしたら、予測に基づいて、スペインの定常性を乱すことで、リズムをこっちに持ってくるしかなかったように思うけれど、ボールホルダーに寄せる際の連動性、それと、相手を !!!っと、混乱させるような技量にいまだ不足していたのだろうか。
あるいは、まづはボールを持ってもらうところからスタート、という手順に忠実過ぎたのだろうか?
……、わけもわからんことを長々、と思われる向きもあるかも知れない。
長い中断、新監督の思想/戦術浸透、復調者、移籍加入などをそっくりほうり込んで、さぁ、となった時、先のスペイン代表にみられたような、新山雅としてこれだけは決して手放さないという〈スタイル〉とは何か?
それが立ち現れるのが、ここ(秋田戦) から 2~3ゲームだろうな、と踏んでいて、
それへの期待と選手起用の謎解きとが、ブラウブリッツ戦プレビュウのすべて、というのが、もったいぶっておきながら、最後は、まことにプアな結論なんであります。
久富、中村、飯尾、谷奥といった、かつて山雅でメシを喰ったプレイヤーに目がいきがちですが、
僕は、コーチ 臼井 弘貴氏(元山雅U18監督/コーチ)、サポートコーチ 熊林 親吾氏(元ザスパ、秋田)、の手腕に興味津々、一体、どういう策をチームに落とし込んでくるんでしょうかね?
では。