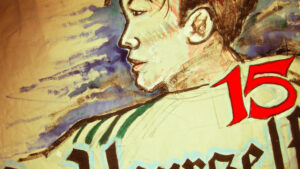ゴール裏の変節、または、退行について、が今回。
負けを責めて、
― 勝つ気あるのか !、とメインや指定席あたりから飛ぶ、単発的なヤジは、(不快ではあるが) かわいいもんだから、それを、いちいちどうこう言わない。
しかし、相当高いレベルで、組織/統合された応援と、求心的な感情の発生する(であろう)南ゴール裏が、
あれほど盛大なBOOをチームに浴びせるとは、
今回、ついに一線を越えたね、という感が深い。
ゲーム後、端から不穏な雰囲気は読み取れたものの、
(気持ちがわからなくもないが) ハッキリ言って、あれは、ない。
あのゲームを、チームの帯同者としてキチンと観ていれば、ああいった対応にはなるまい、というのが僕の考えで、
こうなると、今後、惨敗(際どい負け)をするたびに、BOOを飛ばすことになるんだが、ほんとうに、それでいいのかい?
集団的なBOOをやるならば、そこには、理論的な根拠が必要だと思うけれど、
きっと応援に夢中なためか、おそらく、アタマを使ってゲームをとらえていない。
ひょっとしたら、長野戦の憂鬱を、挽回してくれる、といった期待を裏切られたことへの腹いせ?
あるいは、なんらかの他意を含む?
いずれにしたって、こうだと、ゴール裏は、相当にメンタル的にか細い、ひたすらアンチ長野に生きる諸君の集合体、と受け取るしかない。
これじゃあ、早晩、
こんな成績では、組織応援をやめます、を実践したどこぞのクラブのゴール裏と、精神性の程度において、似たような場所になりそうです。
そもそも、チームに相応の結果を求めるならば、まづは、自分らのエリアを満杯にしてみせる、ってもんでしょう。
北ゴール裏。
僕の隣では、
― ここから、這い上がろうぜ!、と挨拶するチームに檄を飛ばしていた御仁。
萬年の真情は、まったくそれと一致する。
では。