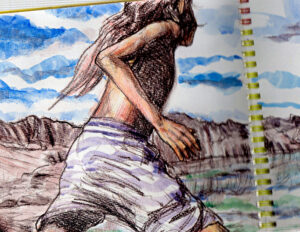サッカーコートと、ほぼ同じくらいの大きさ(底面積)を持つ、国際宇宙ステーション。
これが、7/29,30の両夜、(月齢12~13日の、空の明るさの中) 肉眼で観られたことを、まづは、ご報告しておきます。
愛媛戦については、
こっちが犯した3倍以上のファールを受けながら戦って、
むこうの 約3倍のシュートを打った。
つまり、かなり、ワンサイド的なゲームだった。
この数値は、両者サッカー(観) の違いから発生する話でもあるので、
とにかく。
山雅は、対戦者のスタイルを踏まえたとしても、極端に対処的サッカーに走ることなしに、相手の〈牙〉を抜く、と同時に、こちらの強みでトドメを刺す、これを追求する。
つまり、愛媛戦は、今のやり方をブレることなく遂行せよ、という象徴的なゲームだったように思います。
チームが出来上がるなか、先発メンツに連携が深まれば、今後はその分、交代枠の活用と、交代プレイヤーの力量、これがもっと課題になります。
というのは、ゲーム終盤の被弾ばかりが話題になり、失念されがちなことがあって、
それは、山雅が、全得点の 30% を、76分以降に挙げていること。
(もちろん:、失点が、76分以降に、50%を占めることは、修正事案)
要は。
交代プレイヤーが投入されるにほぼ等しい時間帯に、得失点ともに花ざかりであるからには、
交代カードの切り方が、後半戦では、ますますゲームの帰趨を決めそうです。
ということは、ゲーム強度を考慮して、先発をどこまで引っ張るか?、と表裏一体の話。
では。