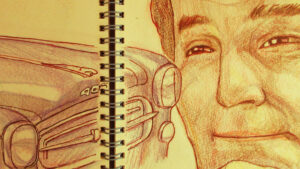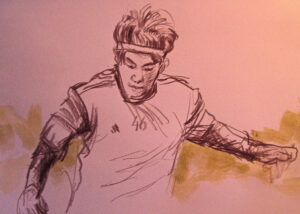〈Aubrey〉は、デヴィッド ゲイツ(米シンガーソングライター)の手による曲。
彼がリーダーを務めたブレッド(バンド名)のアルバム『Guiter Man』(1972年)に収録されて世に出た。
歌詞の冒頭……
And Aubrey was her name
A not so very ordinary girl or name
But who’s to blame?
それでね、オーブリーが その娘の名前
ありきたりでない変わった娘だった、名前もね
でも、それが どうした? って話さ…… (和訳のつもり)
のっけから惹きこまれますが、成就しなかった恋を語っています。
Aubrey は、中世イギリス等では、元来、男性の名(意味は、妖精の王)だった。
が、その後、好まれなくなって(=立ち消える)しまう。
けれど。
20世紀後半、米国で、今度は、女性名として復活する。
実は。
ゲイツは、オードリー ヘプバーン(Audrey Hepburn)主演の
『Breakfast at Tiffany’s』(ティファニーで朝食を、1961年米映画)を観て、この曲を着想したらしい。
つまり、オードリー からの連想で、オーブリー、なわけです。
もちろん。
そんな裏話など引っ張り出さなくとも、楽しめる。
オーブリーとは、ただただ、ゲイツが創り出した女性なんですから。
では。