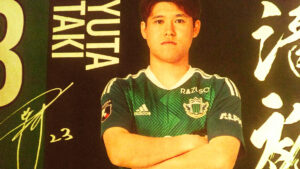(☞ メインスタンドの自陣ゴールライン少し後方あたり、アルウィンだとB自由席ホーム側付近から観戦したことで、プレイを新鮮に観られたのを前提として)
ゲームにおけるポイント。
❶沼津は、ワンアンカー(ボランチひとり)を配した中盤だと思っていたら、
右サイドバックが機をみて上がって、ツーボランチを形成する。
いわば、#18と#3が可変式に中盤を形成するやり方に、ゲーム開始から山雅は押されっぱなしとなり、中盤での劣勢が、終始続いたことは確か。
この運用が、すでに周知なものだったら、山雅サイドの準備不足、といえる。
それでも、1失点した後、山雅は、中盤での劣勢を修正できつつあった。
沼津ボランチへのパスコースに制限をかけながら、米原、安永が動きを多くして、前傾姿勢を強め、
結果、安永がポストを叩くシュートを放ち、右サイドからクロスを入れて小松の得点を演出したのも安永だった。(強く行ったおかげで、米原はイエローをもらう)
この修正を、誰が発案し、誰が呼応して対応したのか。
この点が、これから山雅の財産になるのかどうかは、けっこう興味深い。
❷プレビュウで指摘しましたが、沼津の特長は、歴然と、その左サイド攻撃にある。
ところが、その首脳陣は、反対に左右(訂正します)サイドからの侵入に注力してきた。
山雅は、虚を衝かれた格好になって、先制点を献上した、と診ます。
で、本来の強みである左もあるゆえに、沼津の両サイドの活発はゲームをとおして衰えず、
後半、山雅がその攻撃力を削がれたのは、サイドの対応に追われたことが大きい。
たとえば、僕の周りからは、下川がボールを後方に下げるたんびに、その消極性を責める声が挙がった。
ただ、これは、下川ひとりの責に帰するものでなくて、その内側で連携するプレイヤーのサポートが乏しかった。
こういう部分でも、沼津には、定型的、オートマティカリイな連動性が備わっている。
常田のボール処理が、再三緩慢にみえたり、あるいは、途中交代の野澤が、自分のサイドへボールが送られた際、
― おぉ、こっちへ来るのか、それじぁあ、とプレイに入る時に漂った唐突感。
それは、沼津にはあった意思統一が、こっちには、より希薄(気迫ではない)であったことが表出したものではなかろうか。
❸乱暴な言いですが、キーパーで落としたゲーム。
あと20年も若かったら、ざけんな! 村山、とヤジっていた、きっと。
(三度めの指摘でうんざりもするが) ゴールキーパーの出来がかなり不安定、腑に落ちないプレイが散見された。
たまに発動される沼津のロングボール戦法はけっこう効いたけれど、
それへの対応で、前に出る出ないの判断に、疑問が多く、ひやりとするシーン多し。
1失点目は、おそらく、マイナスの(右サイドから)クロスを想定しての立ち位置を採ったと思うけれど、あれ、狭いニアを割られちゃあマズイ、反応が緩慢過ぎる。
2失点目。〈壁〉を自認するなら、野々村よ。
あそこは、身をよじって(逃げて)、シュートを見送るか?
むしろ、身体を張って止める場面だろう。
ましてや、君がブラインドになってんだから、村山が反応できるわけがない。
3失点目、コーナーキックから打点の高いヘディングが決まると、
家人は、微動だにしない村山を責める声を発したが、まるで八戸戦の二の舞。
キーパーとしては上背に欠ける村山の採り得る体勢はあんなもんだろう、とは思う。
が、それでもなんらかの反応はしてもらいたいよね。
上背うんぬんはともかく、好調時の山雅は、それなりのキーパーを擁した、と思うが、いまのやりくりは、果たして、どうなのか?
永井 堅吾を活かせなかった山雅から、進化していない?
……おおまかなゲーム様相は、挽回はしたものの、やはり沼津の攻撃性という大きな流れを遮断できず、そんなところ。
ポジションからして、それが当たり前なんでしょうが、
ボールを熱心に欲しがり、なんとか突破をもくろむプレイはやはり、
小松、菊井に濃厚であって、(おそらくは) 今季限りとはいえ、彼らを頼って闘う、ってもんか、あと6試合。
では。