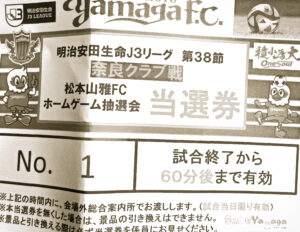チノ氏は、(指揮官)続投について、自分は懐疑的だ、と言う。
― たとえば、守備。
山雅のサイドは、高い位置へとあがりますよね。
さらに、ボランチも、駆け上がる。
そうなると、沼津みたいな、アジリティ(俊敏性)を有した攻撃をしてくる相手だと、
こっちのサイドの裏へと、簡単にボールを運ばれてしまう。
そうすると、残ったセンターバック2枚で対応するような格好になって、失点。
片方のサイドが上がったら、もう片方は低い位置を保ってバランスをとるとかしてもいいのに。
こういうことが(修正されすに)放置されていれば、やはり現指導陣には、疑問符がつきます。
山雅の攻撃は、遅いですし。
で、チノ氏から、攻撃面の不足に関して、どう思うか?、と返された。
― 守備態勢が整った相手の外縁を、それも、足元でボールを動かすばかりの傾向が、ここのところ強い。
やはり、縦にするどくボールを入れて、守備網のほころびを誘うなりしないと。
前は、野々村や常田のチェレンジ性のある早い縦パスがもっとあった。
― 常田の、サイドチェンジもね。
― あとは、やはり中央へボールを持ってきて、そこから撃つ、といった工夫を入れないと、厳しい。
それと、速い攻撃なら、後半に見せた、滝、藤谷ら 3人で右サイドを、パス交換で侵入していく方法。
― 今日の小松はフォワードとしては、不出来。
あの程度なら、榎本と、早く交代すべきです。
トップとしては、渡邉のほうが、ボールの納まりもいいね、とチノ氏。
― そう。どんな体勢からでも、シュートまで持っていくしぶとさがありますよ、渡邉には。
……さて、ここからが、萬年、机上での補足。
サイドからクロスの雨を降らしても、なかなかゴールに結びつかないならば、
ペナルティーエリアに入るあたりでは、地上戦で、3人くらいが絡む。
で、すくなくともひとりは(ボールを持たずに)、相手のディフェンダーを誘き出すように動いて、シュートのスペースとコースを生みださないと、いまの閉塞感は破れない、と思う。
一見、ムダ走り、自分を捨て石に使うプレイ、無用の用です。
とにかく自分で打ちたくなる若いチームであればこそ、こういうのは、指導者が提案しなければ。
現状、最後まで詰め切れずしてフィニッシュに行くので、
どうしても、シュートが強引、不正確になるか、コースが甘い(キーパー真正面とか)。
一時期、
菊井☞小松のホットライン、とか浮かれていたけれど、相手も研究して小松の動きを2~3人で制してくれば、そういった単純な構図では、もはや得点は生まれず、
むしろ、菊井☞小松のそれを、デッドライン化(ある意味で囮)に使って、他の連携でゴールに迫ることを考案しなくては。
では。