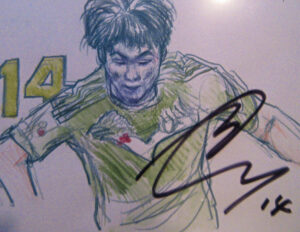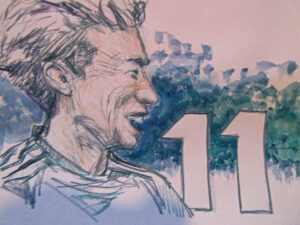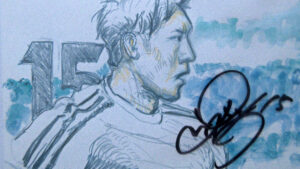
前回の対戦(第3節)では、山雅は、4 – 2 – 3 – 1を採用。
安藤 翼をワントップ、山口 一真を2列目中央に置き、浅川、菊井はベンチスタートだった。そこから、
福島が、シーズン当初から、ほとんど不変なスタイルを貫き通しているのとは、
かなり対照的な道をたどって、つまり、よっぽど試行しながら、
いまや、(福島と)同一の、4 – 1 – 2 – 3 (≒ 4 – 3 – 3)システム、にたどりついた山雅。
(註、と言っても、システムは万能にあらず)
ところで、 0 – 1 で敗れた、あのゲーム。
13分に、中央を割られた縦パスを、#10森に、ドリブルでシュートまで許して先制されると、
同点、逆転を期して、しゃにむに突貫を繰り返した、その結果、
スタッツは……、
ボール保持は、こっちが 58%、パス数は、福島の 1.5 倍を繰り出し、
シュートに至っては、山雅 13(枠内 6)本、対し、福島は、8(枠内 1)本。
どっちが、ボール保持とパスサッカーのチームなのか?、わからないようなゲームでした。
それから、4箇月が経過しての再戦。
萬年的な観点からすれば、
福島は、自流のクオリティを増す、要は、もっと上手くやるつもりで乗り込んでくるだろう。
対し、山雅は、これから上位を追撃するためにも、上手くやる(個の技量を上げる)だけでは物足りず、
アタマを使って、巧く(巧妙に)立ち回って、ゲームをモノにしなきゃあならん。
❶福島のお株を奪うかのような、縦に鋭いパスを、たとえば、米原や野々村から、菊井、安原、安藤に多用するのか。
そして、ペナルティエリアの(ゴールマウス)中央への侵入をめざすのか。
❷相手の攻撃的な前傾を、そのままひっくり返すように、ロングでハイなボール、ビッグスイッチを、相手陣内奧に叩き込んで、空いたスペースを使うのか。
どっちを選ぶのかは、結局のところ、FC大阪戦のように、
相手の意表を衝き、はぐらかすサッカーをいかに表現するか?、に在るはず。
いずれにせよ、自分の陣形は間延びさせず、相手のそれを縦方向に寸断することが必要で。
となると。
中盤で多く奪取をおこなうであろう山本 康浩が、
かつてのチームメイト(磐田) 宮崎 智彦をいかに抑えるのか、そこがひとつのポイントと診ます。
では。