家人、直近の嘆き。
― 降格にでもなったら、あなた達は他のクラブへ移ればいいんでしょうが、こっちは、山雅を乗り換えられないのよ。
まぁ、それも一理ある。
が、もうそろそろ、来季戦力構想外のプレイヤーにはその旨伝えられ始めるんだろうから、お互い様の部分もあるんじゃあないか?
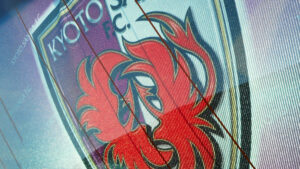
さて、前節(9/4)。
甲府の地で、サンガは 0 – 3 で敗れ、結果、どこかのチームに大勝した磐田に首位を明け渡している。
ハイライト映像を観たら、どしゃぶりの雨を衝いた甲府の、スピードに満ちた攻撃にやられまくった、という感じ。
チームは、一旦京都に帰って、昨日には来松の、中2日の忙しい移動をやりくりしているのか?
日程的には他人事でもない山雅であるから、フレッシュさの点で、登録メンバーの人選は慎重におこないたいところだ。
ゲームプレビュウならば、8/13の投稿から、両者の立ち位置にそれ以降大きな変化があるわけではないので、詳しいことはそれを読んでいただければ幸いです。
要は、遊びもなく、休むことなく、長短織り交ぜながら、どこからでも必殺のボールが、天地かまわず強力なフォワード陣めがけて入ったり、あるいは、ミドルシュートがペナルティエリアを侵してくる ― それがサンガの真骨頂なんであります。
これに対して、我がチームに過分な注文をする気にもなれないけれど、ひとつだけ。
攻撃スピードの欠如、というか、前へ向かう場面での無用な息継ぎ(ノッキング)。
それの原因と思われる、攻撃時に散見される逡巡と、離れ過ぎたり、時にかぶり過ぎたりの、プレイヤーの距離感の悪さ、その修正をみたいものです。
実は、あとひとつの期待があるんですが、こっちは、すぐにはできないか。
それは、〈誘うディフェンス〉。
球際に緩い、という定義は、単にボールホルダーに向かっていかないということではなく、ただただ追従的で正直な守りに徹してしまっている、ということではありませんかねぇ。
相手の攻撃陣に、意識的にスキを与えて、喰いつかせることで、当方に都合のよいエリアへボールを出していく。
これの好見本が、たとえば、大分だったり、タイプは違うけれどヴェルディだったり。
いまのセンタバックのセットには、無理な注文かも知れないが、大量失点のひとつの要因は、狡猾さの無い守備にあると思えてなりません。
攻撃を組み立てる際、たまに〈こすい〉パス回しはするんですが、まだ萌芽レベル。
下がってガチガチに固めて守るスタイルに固執するのでなければ、どうしても踏破したいステップでしょう。
ならば、すぐできることとしては、前線プレイヤーのよるファーストディフェンスの工夫。
パスコースを限定するといった連動性で、相手のボールの出しどころを窮屈にする、それが現実的な方策でありましょうか?
ところで、どういう因果か、明日は非番。
ゆえに今夜は、帰宅時間を気にもせず、アルウィンにおります。
では。






