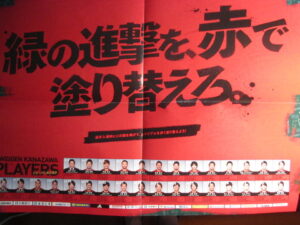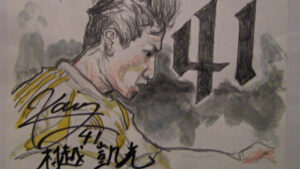
タイトルを、
決して勝てない相手ではない、にしよう、とも思ったが、
それだと。
少々消極的、かつ、筆者の嫌いな、気概論と勘違いされそうだからやめにした。
手を使えないサッカー特有の不安定さで、
得点も、失点も、〈たまたま〉起きてしまう(と思っている)。
(観てる者は、後出しじゃんけんで、勝敗の因果性を語るが、
おおく、自分の心象の吐露、あるいは印象による推断、であることが実に多い)
ま。
どれだけ、その、たまたまなゴールを、
より必然なものへと高める準備をするか?、できることはそれくらいでありましょう。
要は、彼我、互いに技量において隔絶していないのであるから、
前もっての仕込み、現場での修正、それらの一切合切を賭けてやるじゃん、というお話です。
まさに、三か月前。
アウェイのカンセキでは、隙を衝かれた失点で、3 – 1 と敗れはしたが、
内容としては、決してぶざまでもなく、チームを労うべきな敗戦だった。
あれから 90日をかけた進化と深化、それを魅せてもらいましょう。
……ひっかかるのは、
宇都宮の夜、チームに さかんにBOOを浴びせていたアウェイゴール裏の非リアリズムの心理が、
土俵に足がかかった状況下、エキセントリックになってるか?、という点。
ただただ、負けて悔しいを、チームにぶちまけているロマンチストたち。
もちろん。
ファン&サポーターに我慢するとは切ないことだが、
……チームが我慢すべきはゲームでのやりくり。
それは、プレビュウ❷で。
では。