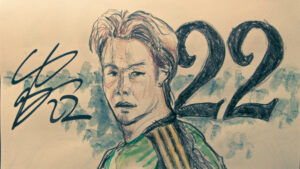― あなたは、いっつも!、あたしの意見を否定するところから入るわね。
と、手厳しく言われ続けている。
僕としたら、
それって、アタリマエのようでも、ちょっと吟味してみないか?、の心算で立ち止まっているのだが、
相手がハローと言ったら、グッドバイ。グッドバイで、こっちは、ハロー。
☞ よって、アマノジャク、という烙印。
……さて。
伊豆半島の東海岸に住む方々は、よほど清廉潔白な人生を歩んできたためであろうか、
清廉潔白を、他の人にも求めて果てしない。
多くの者に、
咄嗟のウソや、誤判断にしがみついたあげく、窮地に立つか、
はたまた、生涯そのことを想いだしては、苦い思いの経験があるのでは?、
と、そんなことのきわめて多い僕は、決めつけている。
小学校の 4、5年のこと。
教室に落ちていた鉛筆を、自分のモノと名乗り出る者がなかったばかりに、
担任がクラスひとりひとりの筆箱を調べ、トコトン犯人捜しをしたことがある。
……結果、僕がその当人ということで、ずいぶん叱責を受けたのだが、
子供ごころに、変につまらんことに執着する奴だ、と教師を哀れに思った。
昔から、教師を敬わないために、彼等から敵視されることが多かったのは、
僕の弱点(例外的な教師もいる)。
本塁突入の決意をした者に対し、ホームベースの一角を開けられないような人格は、指導者になっちゃあいけません。(萬年語録より)
学歴を詐称することは、よろしくないこととは思うが、しかしそれを、
ああだこうだ言うのは、学歴を、よほど偏重する者だろうし、
僕なんか、大学なんか出ていなくたって、首長になれるというのは、
誇るべき希望のひとつではないか、と思っている。
こういうのはですね、誰かが、本人を舞台の袖にでも呼んで、
つい、口から出てしまったのだろうがさぁ……適当な詫びでも入れとけよ、
と諭して、事態を、周辺の皆で、ウヤムヤにしてしまって(収拾)、
早く、次に進んだらどうだろう?、時間と経済と労力のために。
世の中、もっと大切なことが、いたるところでウヤムヤにされてますぜ。
……以上、マジメな向きからは、決して是認されぬこと請け合い……ね。
では。