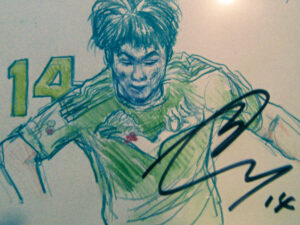
結果は、0 – 0 のドロー。
ラスト20分の、クロス被弾しまくりを観て、負けなかったことが救い、とするのか?
それとも。
ドリブルからのシュート未遂や、ゴールマウス外しをいくつかみせられて、攻撃の未完を責めるのか?
コップに水が半分も残っている、いや、コップには半分しかない、同じ現象なのに、どうとらえるの?、みたく、
観る者の視点が、求めるものの高低、過去の経験による縛り、原因と結果の推定、
そんなものでそれぞれ違うから、サッカー批評は、心象に多くゆさぶられる。
だから、正解など端から期待するな、ってことか。
DAZNで一緒に観戦していた息子に、
前半は、8割方、山雅がゲームを支配していたと思う、と話したら、
猛烈な反駁を受けてしまったが、
おそらくは、息子の期待値が、萬年よりかは遙かに優っているせいだろう。
右に #20、左に #10の突貫タレントを配し、ワントップにボールの納まりの良いタッパあるフォワードを置いて、
山雅の攻撃をひっくり返す格好で、ゴールをめざす宮崎のスタイル。
確かにそれは脅威なんだけれど、やはり、前半は山雅がほぼ制していたと診たい。
ならば、後半は?
後半の、我がチームのあり様を〈失速〉と評するのは、まったく違う。
攻撃の〈勢い〉は、ゲームをとおしてそれほど変わっておらず、
相手の攻撃時間が長いのを〈失速〉と表現するのには賛同しない。
特に、70分以降。
ディフェンシブなタレントを投入し、みづからが守備網を拡げ、ゴール前も固めたのだから。
だから、無失点に抑えたのは、ひとつの成果と評価されるべきで、
入ってくるボールに先手で対応していたのは、ほとんど山雅のほうであった。
そこには、高身長のプレイヤーを活かせない宮崎の不足もあったにせよ。
……で、次節以降のカイゼンのヒントとして、(実現可能な)不足についていくつか。
❶待ち構える態勢は、4 – 2 – 4。
アンツバを欠き、左から、菊井、國分、浅川、村越と並ぶ。
(ただし、#10には、かなりの自由を与える)
菊井を左端に配すのには、そこからの崩しとクロス投入を期待してのことと考えるが、
これが曲者で、おかげで、山本 龍平の立ち位置を希薄にした、つまり、役割りをあいまいにした。
対峙する 宮崎#20の丹念な寄せの前に、それを突破するチャレンジが皆無だったこととあわせ、菊井をオーバーラップして突進する動きに乏しい。
さらに、13分頃、村越が左サイド前方に斜めに走り込んだ際、そこへボールを出さず、後方に下げてしまうには、大いに不満。
サイドで優位性を獲れなかったことで、宮崎のクロス投入を助長した、と言って良い。
で、國分は、本来ボールを左右に捌くボランチタイプであると思うので、最前線に配置するなら、前田、田中でしょう。
となれば、菊井は、2列目の中央トップで、基底に安永、山本 康浩と、正三角形を形成するのがよく、
前線は、山口、浅川、村越 (左右はどっちでも良い)で、が僕のご推奨。
では。





