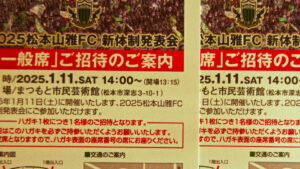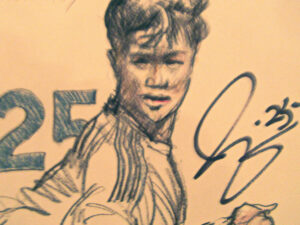
戯れに、現有33人のプレイヤーの平均年齢を算出すると、
これが、23.03歳。
昨季は、25.2歳だったから、かなり若返りました。
その要因のひとつは、30歳台のプレイヤーが、 6人から 4人に減じたこと。
(註 ☞ ただし、ゲーム登録、または、先発の平均年齢は別なので、ゲームコントロールにおける年齢の重みとは違う)
若返りの要因の、ふたつめ。
3部リーグにいるメリットとして、
上位リーグではなかなか出番に恵まれない俊英を、育成型でレンタルしやすいこと。
今季は、4名の加入。
中村 仁郎は、レンタル満了。
で、今季は、FC岐阜に期限付きレンタルのようだ。
再レンタルならば、なぜガンバが、同じ3部に移籍させたのか、おおいに疑問。
2部でもできると思うし、同じリーグなら山雅で良いけどなぁ。
思うに。
個人的には、山雅で続けて観たかったけれど、契約満了にしたのは山雅の側で、
右ウイングでは、村越と佐相の成長があり、この二枚看板で、まづまづメドがたった、ということか。
(ただ、右サイドがそれで十分かというと、そうでもなくて、左右サイドバックの配置、使い分けの工夫がポイント)
若返りの要因、みっつめは、
ユース年代の強化が効いてきて、たとえ大学経由であっても、トップチームへの還流が、ますます顕在化した。
特に、樋口 大輝のルーキーイヤーの活躍は、目に見える成果。
ある意味、小松 蓮の流出をカヴァーして、さらに、お釣りが来たんでは?
予算措置的には、2022年から、アカデミー関連支出が、1億円の規模に達していて、やはり、それなりの費用と時間が要るんですよね、こういうのは。
今季からは、橋内 優也が、指導者として加勢してくれるわけだ。
数年前に、チョコッと耳にした、
〈強化〉と〈育成〉の両輪が、それなりの格好になってきて、
〈松本から世界へ〉を掲げるなら、
この領域だと、山雅のめざす到達点とは、
ピッチに、下部組織の出身者が、5~6人は常在している姿でありましょう。
では。