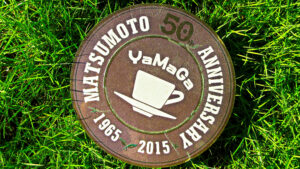〈乱暴な胸算用だと……〉
J2が、22チームで争われている限り、という条件だと、過去実績から……、
トップリーグへの昇格勝ち点の目安は、ゲーム当り2点で、累積 84点。
下部リーグへの降格勝ち点の目安は、おなじく1点で、累積 42点。
……これが、ざっくりとした勝ち点勘定。
残り10試合を切ったあたりから騒ぎ出せ、と以前書いた手前、ここで、こんな算数をしてみる。
現在、山雅のゲーム平均勝ち点は、(ニヤリー)ジャストの 1点。(勝ち点31)
要は、このままの勝ち負けペースで最後まで行くと、ほとんど降格が待っているという現実。
よって、それを回避するには残り10試合で、勝ち点 15(累計で45点) を積むことが至上命題。
つまり、ゲーム当りの勝ち点にすると、 1.5 を獲ること。
これ、けっこう厳しくて、引き分け2試合続けてもおっつかない。
極端な話、1勝1敗の戦績をずっと刻まなければいけません。
もちろん、連勝、あるいは1勝1分すれば違う世界がみえてくるが、今季の我がチームに、それを期待するのは虫のいい話だろう。
たとえ負けを挟んでもいいから、勝ちを貯めることが必要。
つまり、指揮官の言う〈ホーム全勝〉とは、おそらくこの勘定に基づいているはず。
得点しなければ決して勝ちはない、となれば、残り10ゲームは、ゲットゴールにフォーカスを絞る、これしかないのであります。
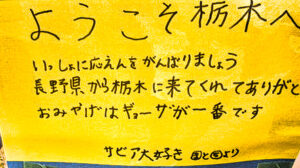
〈踏んだり蹴ったりは、もう嫌だ〉
さて、明後日の栃木戦。
振り返れば、5月第15節のアウェイでは、0 – 3 のミゴトな敗戦でありました。
プレイスキックからヘディング被弾の 2発、ポスト直撃の跳ね返りをニアに撃ち抜かれて 1発。
ゴールキーパー村山は3失点のシーンすべて、すこしは動いてみせろよ!、と思うくらいに棒立ちの酷さ。
さらに、捕球に行った場面では、頭部を足蹴にされたりで、文字通りの、踏んだり蹴ったりの厄災日。
あの後味の悪さ、これをアルウィンでは吹き払うため、その対策については、後編で。
サビアを擁した頃の栃木SCには、とても勝てる気もしなかった。
トップリーグの燃えかすも既にとぼり、金沢や千葉に、やっとこさで引き分けるような山雅の現在地は、その当時に戻ったくらいのことと割り切って参戦だ。
では。