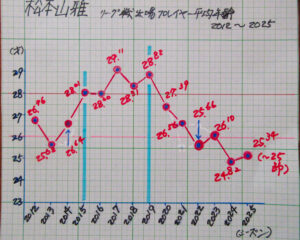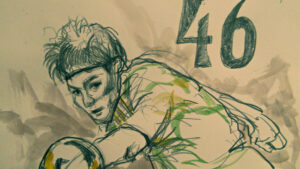もしも、#10菊井 悠介が、あの夜ピッチに立っていたならば、
3 – 0、4 – 0、のスコアで勝利していたのかも知れない。
が。
アシスト、クロス、ドリブル、ラストパスなど攻撃的指標において、
山雅内キングのこの男を欠いていなかったならば、どうだった?、などと、
実は、だあれにも判らない、立証できない話なのだ。
けれど、彼の不在によって、
とりあえずは、一旦、菊池にあづけよう、
そこで、ワンタッチプレイでクサビのラストパスが入るだろう、
常に菊井の立ち位置を見ておこう、
セットプレイは、彼の領分、
……と言った期待や依頼心は、一切、無用のはずだった。
僕には、
やはり彼を欠いた、
昨季のアウェイ大宮戦(2 – 0 の勝利)が想いだされるのだけれど、
あのゲームも、前方向のたたみかけが、チーム内に共有されていて、
お洒落、気の効いた、そんなプレイが皆無だったように記憶する。
それと、ボール保持のチームに対し、ボール保持で上まわるゲームをやってしまった、この前の、ホーム琉球戦(1 – 1のドロー)。
その存在と不在とが、ジス イズ ザ クエッション……。
ならば、どうするか?、って。
月並みにはなりますが、
我らが#10が、
チーム攻守のかなりな部分でタクトを振ることで、チームを牽引しつつも、
そこでは、無駄なく、よどみなく、シンプルに相手ゴールを陥れる手法に執着すること。
ここだけの話、僕が主張する、菊井ボランチ的配置論はそういった趣旨でもある。
なにせ、次節は。
ホーム対戦では、勝利はしたものの、こっちのシュートは 5本と寂しいゲームだった、そのツエ―ゲン金沢と、あのスタジアムやるのですから。
では。