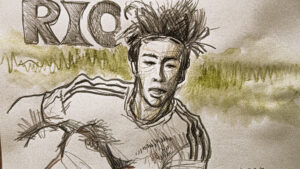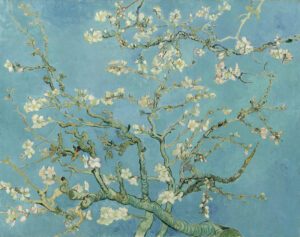ポール サイモン(1941~) による作詞作曲。
同名のアルバム冒頭に収まっていて、のちに、シングルカットされた。
アルバムには、他に、
〈50 Ways to Leave Your Lover〉といった秀曲もある。
いづれも、題名を聞いただけで、ムムっ、とさせられる、良きセンス。
Still Crazy ……を、直訳すると、
〈ずっとやってきたけれど、いまだにクレイジー〉となるが、
☞ すこし意訳を込めてしまって、
『何年経っても、僕はあいかわらず』は、どうでしょう?
……昨夜、通りで 昔の恋人とばったり。
僕をみて、彼女、ずいぶん嬉しそう
で、僕は 微笑んでみせた。
ふたりビールを飲みながら、あの頃のことを話し込んだり。
何年経っても、あぁ、僕はあいかわらず……。
人とのつき合いに憧れるような奴でもなく
むかしからの自分流でやっていきたい男。
かといって、アタマの中に流れるラヴソングを焦がれるほど単純じゃあない。
朝の 4時。
手を叩いて起き出すと、欠伸をしてみる
人生を追いやってしまいたい、などと思いながら。
かまうもんか、そうだろう?
すべては過ぎ去るんだから……。
窓辺にすわって、僕はいま、クルマの流れをみている
素晴らしい日を みづから台無しにするんじゃあないか?、と心配にはなるが
仲間から あれこれと糾弾されるようなことは、ごめんだな。
そう、何年経っても、僕は僕で、あい変わらず……。
元の女とよりを戻すほどの情熱も感じない、昔を偲びはするが、
未来に怖気づいて立ち止まってしまうわけでもない。
……ちょっと見は中途半端で、けれど、やすやすとは自分を譲らない人生。
それこそが自然、と思いたくなる。
アルバムのセッションに参加したメンツを見ると、これが、けっこう豪華。
かつ、ジャズ畑の連中も、チラホラだから、そういう味付けをしたかったわけですな、ポール。
ゆえに、この曲が、いまや、ジャズミュージシャンが好んでカヴァーするのは不思議でもなし。
しかし、萬年的には、
カレン カーペンター(1950~1983年) がカヴァーしていたことで、
曲の価値が深まりもして、それが、発表されたのは、没後の 1996年だった。
ブラッド メルド―(1970年生、ピアニスト)によるカヴァーも捨てがたいですが、
今回は、ニルス ラングレン(1956年生、スェーデンのトロンボーン奏者)によるカヴァー。(歌唱も彼です)
ふたりともが、若い当時、ほぼリアルタイムで影響を受けたであろうクラシックを演っている、と言えますが、
いつまでも、自分に対して〈現役〉で居たいと、つくづく思う。
では。