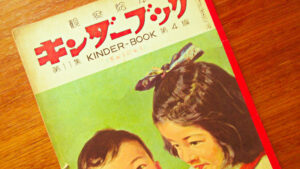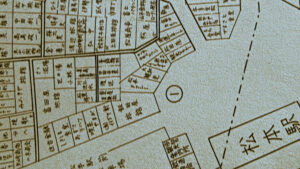(季節の憶え☞アネモネ カナデンシスの 白い花が咲き始めた)
ずいぶん久しぶりに首都の電車に乗った。
あいかわらず、8割強の乗客は、ひたすらスマフォ画面を見続けている。
ひと度画面を開けると、投稿される記事、動画は溢れていて、それに付きあっていれば、時間は容易に過ぎてしまう日常だ。
このならわしをですね、保育園に通う頃から身につけてしまうのだからやっかいで、
チョッと覗き込むと、ゲームセンターで延々と遊んでいる会話だったり、飽食の限りをおもしろ可笑しく脚色したり。
大人向けだと、やたらとセンセーショナルに、自分の境遇を貶めて見せておいて、実は、動画でゼニ儲けを狙う、って手合がめだつ。
あるいは、各所から既情報をかき集めておいて、それを好奇心に訴える呼び込みで引きつける手法。
どれもが、程度の差はあれ、そこには、作画する集団の存在がうかがえるから、これは立派なビジネス。
となれば、それなりに根強い延命はしても、あと3年もすれば、見識に欠け、惰性をまわしているだけの動画は飽きられ、廃れるだろう。
残るのは、こういった新鮮な世界を魅せてくれるものだけでいい。
註:高度17,500フィートは、約53km。
ジェット機の航行高度は10㎞内外で、それを遙かに凌ぐので航空法にひっかからないのか?
昇るよりも、安全に戻ってくることに感動します。
では。