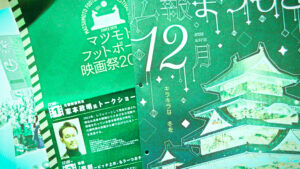政権与党を構成している派閥のひとつで、
政治資金として集めた金を、帳簿外で動かしていたことが判明した、という出来事。
法に照らせば、やっちゃあいけない行為なんだろうが、
僕からすると、他人事でもない失笑、くらいの話題か。
なぜ、他人事でないのか?
数年前、家並み順(=ほぼ輪番制)で、常会長を仰せつかったが、
その期の途中で、某団体からの入金(訂正 ☞ 数万円と記憶) があった。
同様の収入は毎年度発生しているはずだが、引き継ぎされた決算書には、一切記載がない。
前年度の役員に訊いたら、それは数人の役員で分けるように言われた(そうした)、という回答。
いやいや、各戸から徴収する運営費も含まれる会計なんだから、
たとえ、その収入が寄付であっても、記載なくちゃあダメでしょう。
なので、役員手当は、自分を含め、規定額を支出し、
従来、使途不明となっていた収入はそのまま記載して、次年度に引き継いだ。
道理がわかると思われた準リーダー的存在を訪ねて、
― あのやり方は社会通念上、通りませんよ、と伝えると、
俺も、そう思うが……、との返答。
要は、おかしいけれど、今は長老に従うよ、ということなんだろう。
最終的には、長老級と論議になったけれど、正当と思う決算をして、次年度に申し送った。
その翌年。
不明朗な会計が認められるような町会(常会は、町会の下部組織) に所属するのは、自分の信義に反するので脱会しますと、書状を、町会長に届けた。
一応、受け取っておきます、と言うから、
組織の責任者であるあなたに届ければ、それが、正式な通知、即、脱会ですよ、と、僕としては、最大限穏やかにお伝えした。
いまでも、役員山分けの図式が続いているのか知らないけれど、続く限り、
年番制なので、常会の皆が順番にそれに加担していく。
各国会議員は、派閥(幹部)の指示だから、それに従った、と言い訳しているが、
親分(長老)の指示が、法律に優先してまかり通るんだから、
僕のあたりの村落共同体と、自民党は、ほとんど変わりない。
ゆえに、寂しい失笑、です。
では。