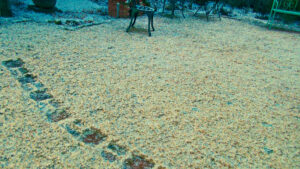松本平を、中山地区あたりの、東山山麓線(県道63号)から一望する。
夕暮れ時、街の灯が点り始めると、
背景には、アルプスの青い山並みが雄大に、デンと在って、
……そのコントラスト、あれは、まさしく絶景に違いない。
家人や息子には、これが決定的〈ふるさとの〉風景なのだそうで。
ところが、
同じ美しさも、僕にとっては、慣れ親しんではいるけれど、
これぞ〈ふるさと〉、とはならない。
いままでの人生で、十数回住むところを変えて来た身からすると、当地に長く居ても、
故郷と、イチオシできる場所がないのが、いやはや。
だから、或る土地(=街)に関して、格別のプライドを持つことも、おおよそない。
どこの場所でも、好きになれる部分と好きになれないところがある、ただそれだけ。
こういう感じは、そうだなぁ、
〈転校生〉になってみないと、なかなか承知できないのかも知れない。
さて、日曜日の対長野戦。
友人で、長野在のカナさん(仮名)が、妹さん親子(母/息子)と、計 3人で、アルウィンで観戦なさる。
姉妹ともに、松本で勤務した経験があることもあるが、
カナさんは、北ゴール裏で、僕たちと一緒に、
つまり、ホーム自由席で、観戦したいのだそうな。
南と北でどうのこうのとか、いい加減にしてもらいたい僕からすれば、こういう感じが好ましい。
煽り文句としての、プライド of 〇〇 は、広いココロでゆるしてあげるけれど、
それに乗っかって青筋立てて騒がしいのには食傷する。
もっとも、
大人の遊びごころで、仲良く喧嘩してみせて盛り上げるのは、歓迎だ。
そして。
それぞれのゴール裏をのぞき、
主催者(=山雅)は、すべての座席を、いまのように混合(服装自由) にしておき、その趣旨を強く押し出すべきではないか。(全ゲームで)
そうすれば、
閑古鳥が鳴いているにもかかわらず、
バックスタンドをアウェイ観客に開放しない某クラブの狭量さが、ミゴトに浮き立つし、
そのクラブが、もしも上位リーグを望むならば、
今のうちからミックス席を設けて観戦者管理に慣れておかねば。
では。