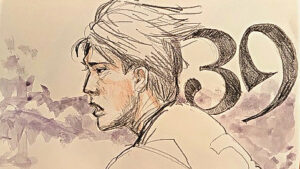技量に不足する者が採用したサッカーを観続けていたら、それが好きになっちゃった、が真相だろうけれど、
誰かが、フト言い出したことが、いつしか、そうでなくてはならない、と固着してしまうのは、なんとも切ない思想統制のようなもの。
勝つと、山雅らしさが戻ったとか、負ければ、それを見失った、とか。
三文記事によるミスリードが跡を絶たないから、今一度、引導を渡しておきたい。
派生的にみれば、40番目のしんがりクラブが、
Jリーグにやって来た後発者として、時間との争いの中、
チームとプレイヤーの最低限な素養、技量に乏しいがゆえのボール奪取への執着、堅守速攻などを備える過程で、
それらが、あたかも、山雅に固有のもの、とみなされた。
だから、カウンター攻撃になったとたんに、観る側のアドレナリンがほとばしるように慣らされる。
ところが、
サッカーが、アソシエーション フットボール(ア式蹴球) である限り、
そこでは、連携のための決め事(規律)、連動するための走力、採るべき守功の方策は、アタリマエのことであるから、
山雅らしさと呼ぶほとんどは、そのまま、サッカーチームに根源たるべき資質であった。
で。
いまチームが取り組む〈再興〉の中身は、
心身ともに屈強な集団を母体にして、ゲームを安定/圧倒的に勝ち切るサッカーの実現、と診る。
それは決して、復古や、先祖がえり、ではない。
僕からすると、新しい指揮理念や、今季の編成、特に、新加入のメンツをみる限り、
かつての #10は、その献身によってたしかに僕らを魅了したが、そこに物足りなかったもの。
すなわち、スマートネスとタフネスをめざす。
フェアに、知力(=スマート) を尽くし、黙々と強靭であらんとする。
#8 深澤、#9 加藤。
名実ともにキャプテンシーを発揮する彼等のプレイスタイルは、それに適う。
ついでに。
〈泥臭い〉への称賛にしても、それは、下手さ拙さの容認につながるものであって、
プレイヤーはあくまで〈上手く〉なるために修練するはずだから、軽々に口にすべき言葉でもなかろう。
ここで。
スペイン1部、直近のゲーム(バルセロナvsレバンテ 2/22)ハイライトを引用。
かたや、25戦20勝の首位。他方は、4勝の19位と、その力量差は歴然としていて、
3 – 0 のスコアだけでは、現わせないバルセロナの〈~らしさ〉 。
いつまでも、山雅を弱者の立場に置きたいのならば、このまま、
〈山雅らしさ〉を喜んでいればいい。
が、めざすべきは、やはり、こういう王道の〈強さ〉だと思う。
では。