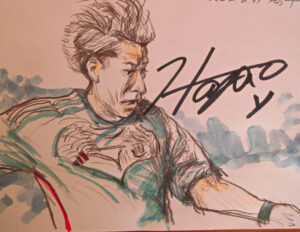5月連戦、その締めのゲームを前に、
プレビュウをおこなうにあたっての戒めとして、
ひとつ。
第4節(5/14)の長野戦、
個の質とサッカーの突き詰めにおいては、山雅 : 長野 = 8 : 2 くらいな違いが明らかになったのだから、
あれだけ相手を圧倒できはしたが、
そこからは、両者間の格差分を差っ引いて、基準器の目盛りを戻さないといけない。
要は、これほどに優位に運べるゲームは、他にほぼ無い、ってこと。
ふたつ。
チームの作り込みの基軸と現在地が、今季は、かなりわかりやすいのだから、
いまだに、3部 = 3流のサッカーといった、いわば〈リーグ天動説〉にハマった視点では、
ますます山雅の真価が、捕捉できなくなった。
……この2点は、肝に銘じておこう。
ただし。
5/14夜のアルウィン全体の反響をみると、
山雅のNOWを、実直、支援的に観られる層が大勢を占めているようであったから、
過去に縛られた思考停止脳を、あまり気にせずとも良いかも知れない。
さて。
今節の来蹴者、ガイナーレ鳥取。
ボールを握ることを本来的として、活発な前線が、俊敏にペナルティエリアを侵してくる、そんなサッカーか。
前節相模原戦(0 – 1の負け)では、スタッツを見る限り、相模原のそれを上回っている。
つまりは、1ミリの油断もゆるされない相手。
そこで、萬年式な願望を、下図に、定着してみた。

〈その要旨〉
❶運用はともかく、初期システムは、ガイナーレと真っ向やりあうつもりで、
3 – 3 – 2 – 2 (3 – 1 – 4 – 2)とする。
アンカー的ワンボランチと、ツートップが、その骨子だ。
特に、鳥取の前線アタッカーの抑え込みは必須なので、3バックで数的優位を保持。
❷メンツ的には、前節、攻撃の基盤をつくって魅せた安永、滝はマストで配置。
石山を、シャドウに置くことで、高い位置で、相手守備に穴を開けたい。
❸菊井へのマークが、ますます厳しくなっていることから、
ここで、コペルニクス的転回(新しい発想)に走って、
菊井をツートップの一角に転用、裏抜け要員としても良いかなぁ、との考え。
もっと踏み込んで、菊井を外してでも、青空を試してみる価値はある。
石山は、その全方向的な躍動力からすれば、フィニッシャーばかりでなく、水を運ぶ役割が期待できるはず。
❹ピッチを広く、均等に使うため、4バックを採りたければ、松村を上げてボランチにまわし、宮部を、左サイドバックに配置する仕込みをしておこう。
……くどいほど繰り返しますが、
より強靭なサッカーのため、あの長野戦は忘れること。
それが、出発点でありましょう。
では。