
さぁ、本日のナイトゲーム。
長野駅と、篠ノ井駅とから、無料シャトルバスが出るとは、ありがたい。
明日は、午前の6時前に出勤。
なので、体力の消耗をなるべく少なくすべく、
ずいぶんと久しぶりに、JRの普通列車を使って、参戦往復することにした。
夏休みの初日にふさわしいようなワクワク感で、車窓を眺めていようかな……。
帰りの電車は、終着駅が、甲府。
寝込んだりして、乗り越してしまわないように、
22時に携帯に着信があるように、保険をかけておこう。
では。


まんねんしきにちじょう

さぁ、本日のナイトゲーム。
長野駅と、篠ノ井駅とから、無料シャトルバスが出るとは、ありがたい。
明日は、午前の6時前に出勤。
なので、体力の消耗をなるべく少なくすべく、
ずいぶんと久しぶりに、JRの普通列車を使って、参戦往復することにした。
夏休みの初日にふさわしいようなワクワク感で、車窓を眺めていようかな……。
帰りの電車は、終着駅が、甲府。
寝込んだりして、乗り越してしまわないように、
22時に携帯に着信があるように、保険をかけておこう。
では。

パルセイロの、直近2ゲームは、
FC大阪、グンマとやって、つづけて、スコアレスドローだった。
山雅が一敗地にまみれたふたつとの対戦を、無失点で切り抜けているのだから、
そこだけにフォーカスすれば、そのサッカーの優秀性を認めるべきだろう。
ただ。
このスコアレス、ってやつが曲者であって、
長野は、我らとの対戦後、8ゲームを消化して、
得点 3、失点 5 (無得点と、無失点の試合が、ともに5つ)。
つまり、被弾をそこそこ抑止してはいるが、得点不足に悩む、ってのが、現状。
極論だと、パルセイロの喫緊の課題は、とにかくゴールを獲ること、それ以外にはないはず。
長野のゲームをほとんど捕捉していない僕だけれど、そのやりたいところは、おそらく、
〈ボールを保持しゴールに直結する速い攻撃〉〈相手陣内で主体的にボールを奪いに行く守備〉、と診る。
近年では、ボール保持を、もっとも高めているといったデータもあって、
その攻守を、3バックでやる。
……なんだよ、それだと、山雅と、大して変わり映えしない、とも言えて、
しかも、相当に攻撃的な意気込みでやってくるだろうことは、目に見えている。
……そうであれば。
乱暴な話、勝敗は、ほとんど、彼我の、個々の技量差で決まってくる。
(その事情は、まさに、サッカーの原理かも知れませんがね)
目の前の相手を、出し抜き、はがし、(正当なチャージで)フッとばしてでも前進せよ。
山雅の戦士よ。
自分たちが開発し、磨き、たくわえてきた自流が表現されて、
そこに、責任有するプレイが継続すること、を願います。
なお。上記〈〉で示してサッカースタイルは、
2週間前、石丸 清隆氏を新監督に迎えた際の公式リリースで、FC岐阜の現場筆頭責任者がステートメントしたものの抜粋。
次節のホーム岐阜戦には、それを標榜するチームがご来松、という次第です。
では。

今節は。
もっとも近くに本拠をかまえるJチームとの、2か月ぶりの再戦。
近距離だからプライドが刺激される心情が、いまひとつ、僕にピンと来ないのは、
どうやら、〈土着性〉を嫌う性向に由来するものだろう。
(☞註:土着性とは、田舎気質のことでなく、都会に住んでいても発生する習性)
まぁ、そんなことはどうでもよく、
ゲームの注目度を上げるためのキャッチコピーなら、どんどん使いまわせばよろしい。
収入増のためには手段を尽くすのが、まっとうな企業のやることだから。
さて。
ガラでもない復習をすると……、
前回のホームでの対戦では、
山雅にとって、今季ベストスリーに入る攻撃的サッカーができた。
シュート 22本は、今季20ゲーム中でトップ。(うち、13本を 61分以降で打った)
ただし。
2得点のひとつは、長野のオウンゴールだから、決定率 4%少々は、いただけない。(ここらへんは、敗戦の福島戦とよく似る)
おそらくは、逆転して気分がノったことがある。
または、長野戦ということで、気持ちが昂ぶったのかも知れない。
ただ。
シュート本数(の多さ) を手放しで喜んでいるのは考えもので、
ゲームによって、(相手の出来もあるが) シュート本数が乱高下するのは、やはり、
チームとして、真の強さ、強靭さをいまだ身にまとっていないからだと思いたい。
それが証拠に、一方では、
180㎝越えの上背とはいえ、その相手ボランチが、ゾーンディフェンスの外から、ノージャンプで打ったヘディングシュートを、完璧に無競合なかっこうで決められる、ひ弱さ。
……調子に乗った時のイケイケの高揚と、なすすべのない失点の同居。
今節は、
こういった不安定が、ここ2か月を経て、
どれほど克服できているのかを、アウェイの地で観させてもらおう、と思っています。
すこしでも高いカイゼン度を望むのは、もちろんで。
では。

奈良クラブが、後半冒頭から、たたみかけてきた戦術的な変更。
前記事ではこれを、変節と、かなり非礼な言い方をしたんですが、
メンツを入れ替えながらも、
ゲーム当初からの、特に、中盤におけるインテンシティを保持しつづけようとした山雅とは、好対照の、
観ていて、面白い、味わいに満ちておりました。
山雅戦では、勝ちとして実らなかったものの、
こういった修正力が、現在、彼らが、我らより上位に在る理由でもありましょう。
3点獲れば完勝で、3失点すれば完敗、とはやし立てる向きには、
ここらへんの綾などは、目に入らないんでしょうが。
けれど、それって、
走れ!走れ!を連呼して止まず、走らなければ山雅にあらず、といった単細胞な見方と同根ですわ。
さて。
奈良クラブ、
初期配置の 4 – 2 – 3 – 1が、
後半からは、
極端にいうと、2 – 3 – 5 くらいになって、前線に4 ~ 5人が一線に並ぶと、
後方から供給されるボールに、すぐにでも反応できる態勢。
そのために、
中島 賢星は後方に落ちて、ボール捌きに、ミドルレンジのシュートに、と専念。
他には。
ボランチの一角が、サイドに出て突貫するとか、あるいは、
右サイドハーフの #7田村から、60°の斜め後方より、山なりのクロスが再三前線に入って、それをヘッドで狙うとか。
……見応えのあるアイデアが、満載。
ひょっとしたら、このチームと再戦があり得る、と覚悟すべきかも。
で。
出場時間は20数分だった、
とはいえ、杉田に替り、左センターバックに入った宮部 大己。
鋭いスルーパスに反応して突進してきた田村に先回りで寄せると、
ゴールラインかつかつで、その身体にボールを蹴り当てて、ゴールキックを獲る。
この沈着なプレイなどで、
ゲーム終盤、相手の攻撃の芽を摘んだことによって、萬年式MIP なんです。
ご本人に訊いたら、左サイドバックは、大学時代にやっていたので苦にならず。
となれば、杉田から宮部への変換は、かなり合理的、かつ効果的。
大学時代の恩師(監督)が、現在のコーチでいらっしゃることでもあるからにはチャンス到来。
#16を背負うことを機に、山雅の魂を、より体現してもらいたいなぁ。
さらに。
それに近いプレイヤーは、
怪我から復帰して、3ゲーム目の 馬渡 和彰。
アウェイ栃木SC戦で、彼がピッチに投入されると、
隣で観ていた家人が、その独特な存在感に打たれたのか?、
― (指さして) #7って誰だっけ?、とおっしゃった。
スロウインひとつとっても、投入の目当てが、実に攻撃的であって、
周囲の受け手の側が、つねに臨戦態勢を採っていないと、きちんと処理できない。
緊張感をチームにみなぎらせるプレイは、ホント貴重です。
では。
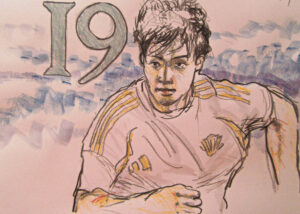
サイドは、終始、奈良のほうが優位に使えていた。
結果、コーナーキックは、山雅は1本のみ。
ボール保持は、常にむこうにあって、時間帯によっては、70%くらいだったと思う。
要は、どっちに転んでもおかしくないゲームだったが、
攻撃の、最後の部分だけを切り取れば、
山雅が放ったシュートはどれも、奈良ゴールキーパーの手が届かないところに突き刺さり、
奈良のそれはみな、大内 一生の真正面か、そのリーチ内に飛んだ、それだけのことなんだけれど、
でも、やはり、勝敗を分けた底流があったはず。
〈ボランチに託されたもの〉
僕が、プレビュウで、1996年生れ対決としたは、
このゲームが、中盤(ボランチ)の出来映えで決まると読んで、
ただ、山本 康裕の不在を決めつけ、安永 玲央と大橋 尚志のセットを予想したからでありまして、
実際は、安永と,復帰した山本が、当夜のスタメンで並んだ。
開始早々。
奈良は、岡田 優希が左サイドから鋭いクロスを蹴り込む。
これを、(あわやオウンゴールで)クリアしたのが、安永。
このシーンこそが象徴だった。
ボランチふたりは、奈良の攻撃の芽を摘むこと、ボールを奪うことに奔走し、
やがては、
加入したての川上 航立を投入してまでも、〈狩人〉のミッションを遂行させ、
彼等はそれにミゴトに応えた。
2得点目は、安永が、相手ボランチからボールを奪取したのが起点。
☜これが、山雅が、中盤に与えた継続的なミッション。
対し。
奈良の中島 賢星は、オフェンシブハーフ(2列目)をやるようになって、今節が、4ゲーム目。
これは、新監督の肝煎りの戦術であり、過去3ゲームは、2勝1分けで結果を残している。
ゲーム前半。
彼は、岡田 優希への決定的スルーパスをとおして魅せたり、幾度となく裏抜けダッシュをかけて、山雅ディフェンダーと駆け引きしている。
で、みづからも2度オフサイドを冒すほどに、攻撃的で、こちらには危険なプレイを繰り出した。
ところが。
後半になると、ふたりの田村(#7と#17)が投入されて、もっぱら岡田と彼らに攻撃の基軸が移ったせいかどうか、中島は、ずっと後方に落ちてプレイするようになった。
僕は、これを、奈良ベンチによる戦術的〈変節〉、つまりは変更、と診ていますが、山雅にとっては、多少とも、相手の攻撃圧が減じたはず。
〈スロウインに落し穴があるとは〉
奈良の、このゲームを決めた、もうひとつの〈変節〉が、スロウイン。
それまで、奈良のスロウインは、投げ入れたボールの取得率が、100%。
サイドバックは、後方のセンターバックめがけて投げるんだから、そうなるのはアタリ前で、
そこからボール保持して、基底からビルドアップを始めるならわし。
ところが、その禁を解いたのか、解かされたのか。
68分頃の、奈良右サイドにおけるスロウインは、はじめて前方に投ぜられたのです。
つまりは、山雅プレイヤーと、ボールを競合する格好で。
この時、飛び込んだ選手同士の接触が、奈良にファールの判定。
71分のダメ押しとなった、村越 凱光のシュートは、このファールによるフリーキックからの一連の流れの中で生れた。
ゆえに、あの時、上がっていた高橋 祥平がボール奪取にかかわり、杉田 隼がアシストを記録したのでした。
ホンのひとつのスローイン……。
……ゲームを決めた、奈良の目立たぬ〈変節〉と、山雅が〈継続して〉最後までボランチに課したタスクについての、対照でした。
では。