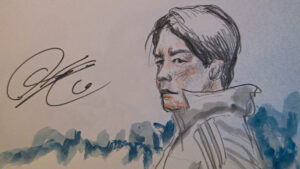
後半アディショナルタイム。
立て続けに、同点と、逆転ゴールとを被弾し、
1 – 2の敗戦。
シーンその❶
ゲームが終わり、篠ノ井駅行きシャトルバスの列で。
隣に並んだ少年に声をかけると、
広丘駅から乗ったという、それも、ひとり観戦な、中学二年生だった。
― こんな負け方するなんて……と彼。
なまじにショックな土壇場劇だったから、
その印象が邪魔をするんだが、同点にされた時点でゲームは決まった。
川西のペナルティキックはオマケであって、勝ち点を 1減じたに過ぎず。
このサッカーをやってる限りは、いま 3部チームのどこと当たっても、
ほぼ順当に負ける、と思う。
実際、讃岐の攻撃には、こっちよりも数段迫力があったし……。
窮鼠は、結局、猫には勝てずだね。
万が一、勝てたとしても、鬱屈と不満は残ったよ、きっと。
……なんてことは、
雨の中たたずむ、その紅顔の少年には、とても言えなかった。
シーンその❷
南ゴール裏(本来は、北)で、お隣りには、20~30代の女性。
― 私、三重から参戦なんです,。
ひとりで、クルマでやって来た、とのこと。
讃岐のほうが、落ち着きがあった、とおっしゃる。
☞ これは、かなり的を得たゲーム評。
指揮官のインタビュウでは、きっと、
南長野をホーム化してくれたファン&サポーターには申し訳ない、から始まるんだろう。
現状のサッカーを見限って、醒めて観ている萬年爺いはどうでもよいが、
その謝罪が、
あの中学二年生、三重からはるばるの女性、
彼等のココロに伝わるものであってほしい、つくづくとね。
無思想な、ジリ貧サッカーとなっても、
山雅には、もちろんつき合いますけれども、
いまのフィールドマネジメントをやってると、
大リーグのワールドシリーズの対戦者は知っていても、
プロ野球の(日本シリーズ)でやってるチームは知らない。
まさか。
松本界隈で、山雅の価値が、そこまで下落することも、あり得るよ。
そのジリ貧サッカーの中身については、プレビュウ❷で。
では。






