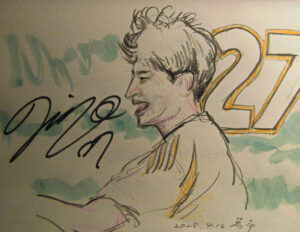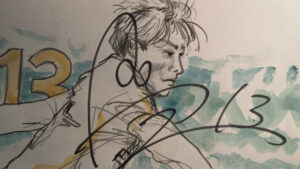
……さてと。
我がチームが進化している部分もあるわけでして、
もともとが、指揮官がディフェンダー出身であることと関係が有るのか、無いのか、
守備面の規律性と (ディフェンダーの)攻撃性が高まったことが、ひとつ。
栃木シティ戦では、3分間で、3回、相手の雑さがあれども、ともかくオフサイドを獲れていた。
センターバックが、サイドバックを追い越す駆け上がりは続けるとして、
あとは。
中盤との連動で、お互いが、パスコースに顔を出してあげる、そういう勇気と、コマメさが増せば良い。
でないと、ボールホルダーのところで、攻撃速度が、かならず鈍化する。
ふたつめ。
パスによって、相手のラインをはがす連携。
この面は、足もとから足元への、各駅停車の、ボール転移が目立った過去2年に比すと、かなり良化されている。
特に、3人目が空いたスペースに素早く入り込むことで、ボールを運べるシーンが多い。
ここでは、大橋を、チームとして巧く活かしている、とも言えるだろう。
アンカー的な仕事も、無難にこなしているし。
アルウィンの雰囲気は、
いまだに、バックパス否定論者が絶えない。
さりとて、
組み立て直しや、相手を揺さぶりたいがためにやる、後方へのパスまで否定されると困ります。
栃木シティ戦における不足は、
山雅のプレイヤーが、互いに良好な距離感(= ソリッドな陣形) の中で、なかなか前へ向かえなかったこと。
(前半の後半は、それができていたが)今後も、この基軸を追求するならば、
相手の陣容の網の目の、粗密になどお構いなく遂行できるようになること。
……さて。
以上を保持しておいて、
その先を、
❶より大胆に(手数をかけるかけない、とは違います)、オートマティカリイにする。
ペナルティエリアに侵入できれば、いちばん。
けれど、ペナルティサークル近くからなら、ゴールマウスの幅(中央へと)ボールを持ってきて、そこからシュートでもいいではありませんか。
前記事でも指摘したとおり、
現状、枠内打ち込み比率はそこそこであっても、シュート本数(絶対値)が伸びておらず、
ひょっとして、
最後の最後、絶好の位置に持ってくるまでは撃たない、撃たせない、という戦略からなんでしょうかね。
❷大内からのロングフィードを多用するなら、それをムダにしない方法の開発。
そもそも、現在稼働できるフォワード陣の特性とマッチングするのか?があろうけれど、
ならば、すべてを頭で競る考えに固執せずに、かつ、
そのセカンドボール回収比率を高めることとセットになった手法(人、スペース)を見い出したい。
では。