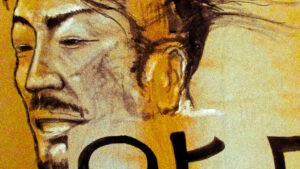註)北ゴール裏の同志チノさんと逢えば、ハーフタイムやゲーム後には、短評合わせみたいなことをやっていて、それがこの投稿に多分に反映しています。
まづ、昨日の投稿を補足します。
僕は、感情的になること自体を否定はしない。
たとえば、日曜日、南ゴール裏では、挨拶にまわるチームに対し、不満、不評の boo が巻き起こり、そこに怒声が交じったり、
はたまた同時に、拍手が湧き起こったりするあり様。
それは、各人の心情が、強制もなく自由率直に吐露されていて、山雅ファン&サポーターの〈健全性〉のあかしだと思っています。
ただ、自分の心象を、闘う選手の姿勢や態度に、勝手に反映し、それを、あたかも事実のごとく断ずるのは、オカシイのでは?、と言いたかった。
さて。
― 残念だったね、昨日は、とか挨拶されたり、
― 山雅はどうだったの?、とか訊かれたり、まぁ、こんなのはフツーで、
きっと、そのスコアにびっくりしたんでしょうね、
― 一体なにがあったのよ?、なんてのもあった月曜日でありました。
それに対する、僕の目撃者としての弁明は、
― いやぁ。
手こずってはいたが、81分までは、ほぼ完璧に近いようなゲーム運びだったんです。
ところが、残り9分間で、勝ちが手からスルりと逃げた、っていう。
90%まではたどり着くが、のこり10%を凌げなかった、そんな感じでしょうか。
学校のテストでは、90点も獲れば、(僕なら) 大いばり。
ところが、サッカーではダメなんですよね、最後に相手より多く得点していないと。
でもね、3点は獲れる、たとえ、先制されてもひっくり返せる、そんなサッカーをやる山雅になりつつある、そこに注目して、今後を楽しみたい。
〈ゲームの基調〉
ゲームの入りには絶好のチャンスが生まれるも、それを逃がすと、
沼津プレイヤーの素晴らしいアジリティ(俊敏性)、長短織り交ぜたボール回し、
特に、相手フォワードと、サイドプレイヤーの寄せの圧力に曝されて、
山雅流前線からの追い込みと、それに連動すべく2列目以降の押し上げが機能せず、非常に窮屈な状況に追い込まれた。
たとえば、ボランチ住田。
彼は、相手の圧を回避しようとしたのか、本来ならば、センターバックふたりの真ん中、あるいは、その前方に位置してボールを受け、前へと進路を見いだすべくボールを捌くのに、あの時は、常田と山本を結ぶ線状に張ってしまい、かえって連携を阻害した。
そのセンターバックにしても、相手の速い寄せの前に、プレイから余裕がなくなり、かつ、普段のパススピードには、なかなか達しない。
ただし、この閉塞状態は、前半30分頃から幾分は改善され、住田とパウリ―ニョに活きたプレイが戻りつつあった。
手こずってはいたが、逆境に抗しつつ、2点(小松、榎本) を挽回。
ゲーム内修正力、これは最近になって目立つ財産で、これからのリーグ戦で大きな武器になりそう。
〈84分の交代は、やはり采配ミス〉
下川を、右サイドバックで途中投入は、これは、ヒット。
そのクロスが、ゴール左で待ち構えた山本のヘッドにドンピシャでミート(81分)して、逆転弾となる。
問題は、その直後、84分の2枚替え。
得点を挙げ、ようやく蘇生のキッカケをつかんだプレイヤーをピッチから下げてしまうのには疑問が残るし、
そもそも榎本が去ったことによって、フォワードから高さがひとつ、消失。
これが、マークの弱さとなり、コーナーキックからのヘディング被弾の伏線となったと診ます。
前々から、交代枠の活用がゲーム帰趨の重要な要件、と思っていますが、
今回の84分交代は、チームへの活きたメッセージを伴っておらず、采配の妥当性に疑義を呈しておきます。
ただ、どうしようもない難題でもないはずなんで、改善を乞う。
ゴン中山アスルのサッカーに、今回は一敗地に塗れるも、更に成長したあげくに、後半戦(10/22) では、愛鷹で、オカエシさ !!
では。