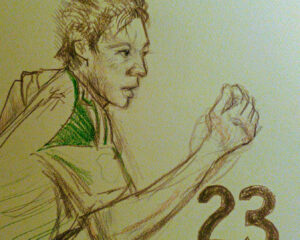終わってみれば、1 – 4 のスコア。
2部リーグ体験者とはいえ、それほどの強烈さを感じさせない対戦相手に、この結果。
……、というのが、いちばんの感想でしょうか。
チノ氏に言わせると、
前半、ゆるく来た岩手に、変につきあってしまい、陣形がたてよこにルーズになった、
つまり、自由に使えるスペースを与えての、2失点。
そして、僕の診立てだと、80分過ぎての失点というのは、飽き飽きしたデジャヴのひとつ。
まるで、前節の(野々村がやった)お返しのような打点高いヘディング(3点目) が決まると、
かなり多くの観客が、スッと、席を立っていった。
1 – 2 の場合、次の点がどっちに入るかで、大勢が決す、というリアルと、
そうなれば、今の山雅にはそれを挽回する力量もないことは、皆さんよく知っていらっしゃる。
冷たい雨を理由にはできない、何か。
象徴的だったのは、選手挨拶の際の、南ゴール裏。
(そういうのは歓迎しませんけれど)、盛大なBOOも起らず。
北ゴール裏からみて、それが怒声なのが鼓舞なのか、おそらくは、後者だったんでしょうが、てんでんばらばらの発声が起こるばかり。
まるで、落胆をおそれて深い没入を避けようとするかのような退潮と、散発的なかけ声と。
戦績が思わしくないから、3部リーグにいるからと、
観客数やスタジアムの高潮感の減少について、クラブやチームを責める向きがあるらしいけれど、
鼓舞するスタジアムを演出できるのは、観ている側の特権であるから、
〈勝たせられない〉アルウィンは、やっぱり、僕らの力不足の結果、と思う。
まっさらな観戦のウキウキ感を、いつしか、どこかに、置き忘れてきたのかも知れない、山雅界隈は。
さあ、これから!!、といった成長途上にある3部のチームを観るにつけ、
そういう〈初心〉を取り戻さないとなぁ、と思いつつ、
RAZUSO更新と、トミカ山雅バス入手の、義務を果たした感のまま、
スタジアムを後にしました。
では。(サッカーの話は❷で)