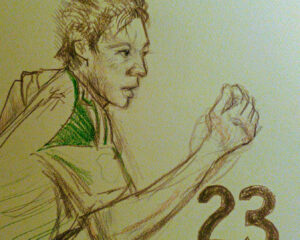初期布陣は、4 – 2 – 1 – 3 。
その後、
交代カードの切り方がチト凝っていて、それを、システム変更をからませながらやった。

❶山口 一真は、稼働時間を延ばすべく、後半アタマから投入。
一真は、攻撃のギアを上げることができるタレント、とつくづく思って観ていた。
ポジションを譲った野澤 零温は、この日、中央寄りの位置取りが多く、もっとサイドへ展開すれば面白かったし、藤谷 壮との連携もイマイチ。
❷67分、藤谷に代えて、滝 裕太を入れると、山口を右へ回し、システムを3バックにすることで、下川を一列下げて、左センターバックへと配転。
しかし、僕は、滝を左、山口を右に置くほうが、彼らがもっと活きる、と思う。
❸76分、村越 凱光に代え、鈴木 国友。
下川に代えて、橋内 優也(センターバックの中央) を入れる。
同時に、3 – 4 – 2 – 1 へ変更して、ボランチを、米原 秀亮と、1列下げた菊井 悠介のセットに変更。
で、住田 将は、今度は、左サイドバックを担う。(住田サイドバックは、2度目の記憶)
この変更について、チノ氏は、村越がピッチから退いたのは疑問で、
かつ、菊井は下げずに、小松 蓮、山口との三角関係で攻撃を創ったほうが良かったよ、との評。
……勝ち点3が獲れなかったのはすべて自分の責任、と霜田さんが言うのは、以上、いろいろと策を駆使したものの、それが実らなかったことを指しているのだろう。
裏返せば、監督のできることの限界、つまり、その先の個々のパフォーマンスはプレイヤ責任が大、とも吐露しているようなもの。
ただし、いくらやってみても。
❶陣形が、特に、タテ方向に間延びすると、今の山雅のやり方では、いかなるシステムや配置でも、その効果が出ない。
中盤における強度が減衰し、セカンドボールを獲れない。
安永 玲央の不在がどうだったんでしょうね?、今のやり方の中で。
❷攻撃の最後の部分に、これで決める!!、といった確固とした〈型〉が、いまだ確立していない。
たとえば、いろんな角度、ボールの質で、異なるエリアに、けっこう良質なクロスは投入される。
けれど。
それに呼応して中央に入るプレイとの間に、
即応や一貫性、習熟度がなく、その時々の、一回限りの、偶然発生のチャンス、とみなしている風が、あからさま。
出たとこ勝負であって、多彩はあるが、仕事としての整然な完遂がない。
米原のアシストキック、あれがクロスとカウントされるのかは不明だが、
クロスを25本入れて、得点につながらない、ってのはないわ。
特に岩手戦では、前線の押し上げがとても遅く、ペナルティエリアへの侵入に力強さを欠いた。
かつて、横浜Fマリノスのピッチ練習(@アルウィン)。
こんなに手の内を明かしていいの?、くらいにクロスからのシュートを繰り返ししていた、その迫力。
残念ですが、我らとは、なにかとスッポンの差。
でも、そこを目指さなくてどうするよ?、下條さん。
手早く前にならば、もっとスピードをあげるべきだし、
時間を使うならば、もっとパス出しと受けに、丁寧と精密がなければ、ミス多発。
たとえ、3部リーグであっても、相手守備網は、そうそう崩せません。
❸再度、指摘します。
村山 智彦は、そのリーチ内であれば、抜群の阻止能力を持つ。(特に1対1)
が、(おそらくは)備えの位置取りの悪さがあって、
リーチ外のボールに、ほとんど動けず、反応できず、
多くは、逆モーションになってしまい、ボールタッチに行けてない。
八戸戦のペナルティキック被弾で、その反応速度の衰えもハッキリしてるわけだから、このあたり、検討課題だと思いますがね。
❹サッカーは、相手の出方によってゲームコントロールしなければならず、
今の山雅において、ピッチ上に、
そのプレイによって、ゲームの流れを切ったり入れたりできる個性は期待できず。
(たとえば、岩手では、センターバックの田代 真一が、要らぬ補水で意識的に時間をすすませるなどの狡猾さで、レフェリーの上をいっていた)
こうなったら、あと8ゲーム。
虚飾のない実直で、押しまくるってことか、山雅。
……以上、すこしばかり(長々と?)サッカーの話でした。
では。