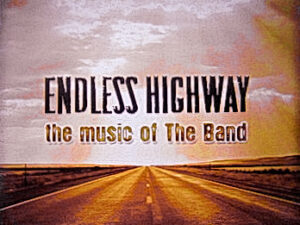ここ数日来、せいぜいその内容はハイライト映像で観るくらいなんだが、大量得点ゲームの報せが多い。
大宮 4 : 長崎 0 (3/27)
新潟 7 : 東京ヴェルディ 0 (3/27)
これらは、同じリーグの話ゆえに、けっこう胸が高鳴るけれど、むしろ大量失点した側の心情が思いやられてしまう。
海外に目を向けると、リーガ エスパニョラ (スペイン1部)では、
レアル ソシエダ 1 : FCバルセロナ 6 (3/21)
ダビド シルヴァを擁し5位あたりで健闘しているソシエダがまさか、とは思ったが、このゲーム、シルバはベンチ入りさえしていなかった。
6点も獲れば、最後のほうは得点時のセレブレーションはごく醒めたものになるもんだが、全員がきっかりとひとつに集まってくる律義さ。
入れて当然、といったスタープレイヤーの驕りを、全く感じさせないバルサには、感動する。
こういうゲームが気にかかるのは、おそらく得点産出に苦しむ我がチームのことが、抜けないトゲのように、いつもココロの底に在るからだ、きっと。
4~5年来ずっと、得点の乏しい山雅であるから、ここへ来てことさら気にすることでもないはずだが、〈新生〉に、いつかしら得点力の向上、を勝手に描き込んでいる自分がいる。
本日のアウェイ水戸戦にしたって、自分を失わずに平常心でプレイすれば良く、出口の勝敗をあれこれ気にするな、とチームには申し上げたい。
雨中、水戸へ出向くチームとファンサポーターには、心から感謝します。
こんなことを寝転がって考えていたら、ちょうど今から100年前に書かれた短編の末尾が、胸に去来した。
〈希望は本来有というものでもなく、無というものでもない。これこそ地上の道のように、初めから道があるのではないが、歩く人が多くなると初めて道が出来る〉(『故郷』魯迅 井上紅梅 訳)
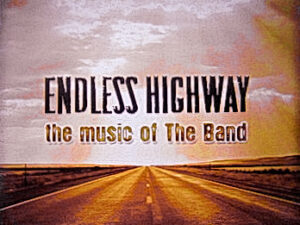
では。