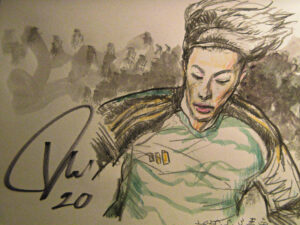
ひとつ。
このゲームに絞っての準備。
登録メンバーは、前節をほとんど踏襲する。
初期布陣は、やっぱり 3 – 4 – 2 – 1 かな。
運用では、中盤を3 – 4 – 3で締めておいて、奪取、即反転をかけたいだろう。
ただし。
この陣形と、ロングフィード戦法とが、どうやって調和することで、
こっちにボールを引っ張れるのか? のロジックが、僕には理解できていない。
そもそもロングフィードの、ボール回収における成功率が、低過ぎる。
エリア的なポイントは、
大阪が 4バックを採るので、ふたりのセンターバックの両脇に空くスペース。
そこにどう入っていくのか。
大内からは、左サイドバック(=タッチライン)へとボールが供給されるとしたら、
そこには、龍平よりも、樋口の〈アタマ〉を用意しておいて、
右サイドは、馬渡☞佐相、のつなぎでよい。(大阪の左サイドへの抑止にもなる)
とにかく、相手の基底ラインを引き延ばして、その〈疎〉を衝こう。
どうやら、最近の山雅は、ペナルティエリアに入るまでシュートは禁じ手のよう(理解できないが) だから、
サイド深く入り込んで、そこから中を衝く、ってことで。
ふたつめは、来季への道筋。
(霜田体制 3年目の集大成があってよかった論者の)ソネさんによれば、
早川サッカーの評価は、
今シーズンの編成に、どれほど現監督の意向が反映していたのか?、が外せない……。
が。
3位にはなったものの勝ち点がせいぜい60点台、との先季の社長総括からすれば、
今季の50点未満は、言い訳の余地がまったくなし。
昨季の主要メンバーがほとんど残留したことに対し、
おおかたの者は、安堵と頼もしさを感じたはずなんだが、
昨季の〈脆さ〉〈耐性不足〉〈一辺倒〉をいまだ引き摺っているから、
皮肉にも、既知の編成が裏目に出る格好で、
❶個の技量の向上はあったろうが、❷そのオーガナイズに欠けた、と診る。
❶と❷の統合が具現化される体制つくり。
これが、準備着手の大前提でしょう。
でないと、昇格の言葉だけがひとり歩きで、実態が追いつかん。
でもさ。
来年から再来年にかけての、スタッフとプレイヤーとの契約年数は、
はたして、1年半なのか?
また、移籍ウインドウは、どう設けられるの?……わからん、わからん。
では。

