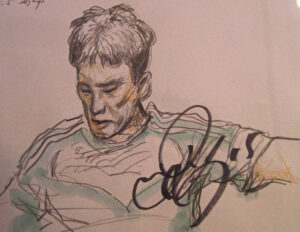
対ギラヴァンツ戦における特筆事項は、
プレイにおいて、選手間における〈齟齬〉があまりみられなかったこと。
僕らは観ているばかりの立場。
なので、たとえば。
あるパスが供給された時、それが、だあれもいないスペースに転々とすると、蹴ったほうのトンチンカンさを、パスミス(過失)として責めたくなるが、
いや、待て、実際は。
あらかじめの決め事で、そこに誰か(=受け手となるべき者)が走り込むはずが、それを逸してしまったのかも知れない。
また、たとえ戦術で決められようとも、一瞬の判断によるプレイが、個々の創造力(それが否定されていないことを願うが)を加味した格好で繰り出されるとすれば、
有機的に攻守が組み立っていくための、決定的な要素は、事前準備の有無にかかわらず、
ピッチに立つ者同士の、他者理解に違いない。
こう考えると、ギラヴァンツ戦の、ギクシャクしたプレイの少なさは、
ここ数試合で固まってきた、先発(と途中投入)メンツに、意思疎通が強固になりつつある、と思いたいところ。
もちろん、誰が投入されようと、同じ理解度で闘える、との願望を込めて。
その、いくつかを挙げると……
❶攻撃の基底部のタクトを振るのは、山本 康裕である!!
あのゲームの、山雅が攻撃に入るシーン。
つまり、山本が、ピッチの中央で受けて、適宜ボールを左右にさばくのを観て
ハッと感じた。
まぁ、今頃になって、しみじみ思う僕が迂闊なんだけれど、
攻撃の重低音は、彼が担っている。
高知戦だったか、チノ氏が、
山本がピッチから消えると、攻撃がバラバラになった、とはこのこと。
特に、右サイドバックの小川へのボール供給は、絶妙のタイミングを狙っていて、ここらは、ジュビロで深めた互いの理解が、モノを言う。
そして。
菊井は、最後の仕上げのひとつ手前の、スイッチを入れるミッションを担っていて、このゲーム、先制点のアシストはやってのけたが、
それ以外の本来の仕事の出来は、守備面では大きかったが、攻めるためのボール運びでは精彩を欠いた。
相手も、菊井がキーマンであるとわかっていて、ひたすら菊井を止めに来るから致し方ないこともあるけれど、
彼を自由にさせるため、誰かが、その前でなにかひと手間入れる必要があろう、特に、左サイドを侵入する際は。
❷二ノ宮 慈洋と、松村 厳のセンターバック起用には、メドがたった。
このゲームにおける、沈着でスピーディなボール扱いは、急速な成長と、ゲーム慣れを感じさせる。
といっても、いまだ発展途上と考えれば、よりシュアなプレイが習慣化するようにと願うが、ふたりの特性からは、これから、
〈攻める守備〉を身につけられれば、グッド。
そこには、みずからの攻撃参加も、もちろんあるが、
相手フォワードを、こっちに有利に誘導して、その動きを無力化するような守り。
田中パウロにやられた、あの失点シーン。
あの時、二ノ宮の右手には、栃木フォワードらが2名走り込んでいたから、二ノ宮は、田中がそちらへパスを出すことも想定していたはず。
それがあって、無闇には田中にチャージできなかっただろう。
だが。
田中の意地(特質)やお膳立てされた舞台からすると、
パウロはかならず自分自身でニアに撃つ、と決めつけ、
ファー側のシュートコースを切ることもできたのではないだろうか?
大内がボール運びを視認するためにも。
それ、後付けの理屈だろう、といえばそれまでかも知れませんが、
対峙する攻撃手の心理を読んで、その意図をつぶす、そんな果敢さを、二ノ宮や松村は持っていると思いますね、そのプレイをみるにつけ。
あとは、田中 想来の、広いスペースを守功に走り回れる有能、も挙げておきます。
では。

